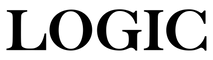LOGIC MAGAZINE Vol.16

LOGIC|SHARE
今、読者の皆さんと一緒に考えたいと感じた
ホットなトピック
LOGIC MAGAZINE 1周年記念タブロイド版完成!

ちょうど1年前、わたしたちの「LOGIC MAGAZINE」は、仕事のパフォーマンスアップに役立つことを目的とするニュースレター型メディアとして誕生しました。
今月で迎えた1周年を記念し、数量限定でタブロイド版を発行します。これまでのLOGICの歩みや、反響が大きかったインタビュー、コンテンツをぎゅっと詰め込んだ保存版で、シリアルナンバー入りです。1周年記念号は、LOGICをご愛用の方、希望者に無料でお届けいたします。
LOGICの非購入者で、LOGIC MAGAZINE読者の方でお届けを希望する方は以下のボタンから申し込みください。
2年目のLOGIC MAGAZINEもよりパフォーマンスアップに役立つコンテンツを提供していきますので、今後のご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
お申し込みはこちらから
※LOGIC購入経験がある方はお申込不要です。
※お申し込みの締切:2021年9月15日まで
LOGIC | PEOPLE
第一線で活躍するプロフェッショナルの体験や知見から
パフォーマンスアップにつながるヒントを学ぶ。

016
Red Yellow And Green株式会社
細井優氏
LOGIC MAGAZINE第16回インタビューにご登場いただくのは、プラントベースフード「Grino」を運営するRed Yellow And Green株式会社の細井優氏です。「持続可能な地球をつくる」というビジョンのもと、植物性食品の開発を進めている細井氏。そこには人間と食料と環境を取り巻く複雑な問題があった。難題の解決に挑む細井氏の“夢中”に迫る。(聞き手:LOGIC MAGAZINE編集部 佐々木、村上)
未来の子どもたちのために何ができるか、
その答えが食料問題だった
―どうして細井さんは「プラントベースフード(植物性食品)」の開発に取り組もうと考えたのでしょうか?
細井:もともと僕は、企業にサラダを定期的に配送する事業に取り組んでいたのですが、2020年初頭に新型コロナウイルスが蔓延した結果、契約している企業の多くがリモートワークに移行してしまったんですね。ビジネスモデルが一気に崩れてしまって、次の一手を考えなくてはいけなくなりました。しばらく暗中模索していたところ、2020年の8月頃にネットフリックスで『Cowspiracy: サステイナビリティ(持続可能性)の秘密』という工場式農業の課題を取り上げたドキュメンタリーを観て、すごく衝撃を受けたんです。たとえば、牛や羊は食事の際にメタンガスを排出していて、二酸化炭素の約20倍の温暖化効果があると言われています。これは自動車や飛行機などが排出する総量に匹敵するらしくて。また、飼料の生産のために森を切り拓くこともあって、アマゾンでは1分間にサッカーコート1.5面分も消失しているという説もあります。
―そんなに!?
細井:現在の世界人口は約80億人ですが、近い将来には100億人近くなると言われていて、単純計算で20億人増えるわけじゃないですか。その分を補うために家畜の数を増やしたら、さらにメタンガスの排出を増やすことになります。
―さらに地球温暖化を早めることになるわけですね。
細井:IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、人間活動の温暖化への影響は疑う余地がないと断定していて、このままだと2021~40年に産業革命前と比べて1.5℃ほど気温は上昇するだろうと発表しています。それだけでなく、100年後には地球の気温が4.8℃も上昇するのではないかという危惧もあって。それくらい僕たちの食生活は地球に負荷をかける仕組みになっているんです。僕には子どもが二人いるのですが、このままの状態で迎える未来のことを考えるがすごく不安になったんですね。
―悲観的な未来を過ごさせるのは嫌だ、と。
細井:サン・テグジュペリの「地球は先祖から受け継いでいるのではない。子どもたちから借りたものだ。」という言葉はまさにそうだなと。つまり、僕たちの行動が子どもたちの未来につながっているわけです。そう考えたら、まだなんとかなるかもしれない今こそ、行動しなきゃいけないと思ったんですよね。この状況を打破するためには、再生可能エネルギーを使うとか、電気自動車に乗り換えるとか、さまざまな取り組みが必要なんですが、そのなかで僕たちは食の領域で取り組みたいなと考えました。週に幾度か食事を植物性食品に切り替えれば環境への負荷は下げられると思うんですよね。
個人の利益にもなって、地球にも良いという状況をつくりたい
ープラントベースフードが広まることで農業の仕組みも変わるのでしょうか?
細井:それは実現したい未来のひとつですね。僕の目標でもあるパタゴニアは、プロヴィジョンズという食品事業で環境再生型有機農業に取り組んでいて、アライアンスも組んでいて。実は農業のなかでも環境負荷の高いものと低いものがあるんですよ。たとえば、多年生植物は土を掘り起こさないので環境負荷が低いと言われています。というのも、土の中には二酸化炭素が固定されているんですけど、土を掘り起こす耕起栽培だと一気に放出することになるんですね。また、肥料や農薬は短期的に見ると農作物の収穫に寄与するのですが、長期的に見ると土地を枯らす原因になるし、土の中にいる微生物を殺してしまうので実は良くなくて。というのも、植物が土壌の微生物に炭素を与える一方で、微生物は植物にミネラルを与えるんです。粘着性の炭素化合物を微生物は生み出し、微生物は土中に穴をつくって空気と水の流れを操る。それによって炭素が土壌に定着する仕組みになっています。そういうことをしっかり認識している農家と取り引きするようになると、農業の仕組み自体が変わっていくと思います。
ー現在はどのようなことに取り組んでいるのでしょうか?
細井:メニュー開発が中心です。いろんなお客さまにヒアリングしながら、改善を繰り返している最中ですね。今までは主菜・副菜を別々に用意していたんですけど、もっと手軽に食べられる弁当タイプのものをつくっています。あとはまだ構想段階ですが、パーソナライズの要素も加えたいですね。
ーこの先、プラントベースフードの認知を広めていくための方法も考えていますか?
細井:実際のところ、地球環境を改善するために慣れ親しんだ食事を変えるのは、まだハードルが高いと思うんですよ。じゃあどうすればいいのかというと、個人の利益になって、しかも結果的に地球環境に寄与する状況をつくりたいなと。現在つくっている弁当も栄養バランスと利便性の両立を考えてつくっていて。そうした身近な課題を解決していく先に、地球環境の改善もあると思うんですよね。
______________
細井優さんのパフォーマンスアップのためのルーティーン
「音声コンテンツをながら聴きする」
移動するときやランニングするときに音声コンテンツを聴いています。分厚い本は読むのに膨大な時間が取られるので敬遠しがちになってしまうのですが、音声コンテンツだとほかのことをしながらでも内容が頭に入ってくるので便利なんですよね。あと「COTEN RADIO」という歴史を解説するポッドキャストがすごくおもしろくてお気に入りです。世界史に興味が湧きました。
細井優さんののおすすめのワークツール
「アイテマス」
最近使っている日程調整アプリです。Googleカレンダーと同期させると自動で予定を組み込んでくれるので、口約束だけしてカレンダーに入れ忘れるようなミスが減りました。すごく重宝しています。
LOGIC | CULTURE
教養としてのカルチャーを楽しみながら学ぶ。

「アートのロジック」第5回
『キュビスム』
知ってるようで知らないアートを読み解く連載「アートのロジック」。第5回は、画家のパブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックが切り拓いたキュビズムです。さまざまな芸術活動に影響を与えたこの運動の歴史や意義を紹介します。
キュビスムは、パリで活動していた画家のパブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックが1907年頃から展開した絵画の動向です。日本では「立体(キューブ)派」とも呼ばれます。
「キュビスム」と聞くと、綺麗な風景画などとはかけ離れたごちゃごちゃした絵を想起して、「あの何が描かれているのかわからない絵か」という思いを抱く人も少なくないのではないでしょうか。それはある意味自然なことです。印象派が「感覚」を重視する動きだったのに対して、キュビスムは「知覚」に重きを置いていました。しかし、その知性的な絵画は西洋美術の伝統に大きな変革を突きつけ、20世紀の多くの芸術表現に刺激を与えたのです。
この動向は1907年、それぞれに新しい絵画のあり方を模索していたピカソとブラックが出会ったことで始まります。ピカソはこの時期、アフリカやイベリアの彫刻に強い関心を寄せていました。自分とは異なる造形感覚を持った彫刻群。そんな関心が強烈に現れた1907年発表の絵画《アヴィニョンの娘たち》は、20世紀でも屈指の問題作です。三次元性や古典的な人体の「美しさ」を無視した画面は、画家仲間も戸惑わせました。正面と横顔を同時に持つ多視点で描かれた人物が登場することから、本作をキュビスムの始まりとすることもあります。
ピカソとブラックは先輩のセザンヌの仕事にも注目しました。とくにブラックは、「自然を円柱と球と円錐によって扱う」という言葉で知られるセザンヌを追うように、風景を幾何形態として捉える絵画を制作。1908年の《エスタックの家》はその代表例ですが、こうした作品を見た批評家が「ブラックはすべてをキューブに還元する」と揶揄を込めて評したことが、キュビスムという名称の由来となりました。しかし、ピカソとブラックは互いの仕事に共通の方向性を感じ、協働を始めることになります。
キュビスムは、「初期キュビスム」「分析的キュビスム」「総合的キュビスム」の三つの時期に分かれます。二人が深く交流を始めた1908年から1909年夏頃までの「初期キュビスム」は、《エスタックの家》のように、まだ対象や三次元空間の名残が残っていました。
しかし、その後に展開された「分析的キュビスム」では、対象は一層細かな部分に解体されました。ピカソとブラックは、ルネサンス以来続く、風景を「見えるままに描く」技術である遠近法を捨て、対象をいくつもの角度から見た形態に分解し、それを画面上で接合しました。それは「見えるままに描く」のではなく、対象に関する知識を画面上で統合する描き方と言えます。キュビスムが感覚よりも知覚を重視するとは、こうしたことを指します。
また、そうした方法論は、二次元上に「三次元空間のイリュージョン」(いわば「嘘」)を立ち上げる遠近法に対して、あくまで二次元に留まりつつ、そこにいかに「絵画的な空間」を広げられるかという挑戦でもありました。ピカソたちがそうした絵と現実の関係性に関心を持っていたことは、彼らが「トロンプ・ルイユ」という騙し絵的な表現を導入していることにも見て取れます。そうした絵画独自の空間への問題意識は、のちの抽象絵画にも引き継がれました。
キュビスムの絵画のまた一つの特徴は、その色彩の乏しさです。ピカソたちは形と空間の探求に焦点を当てるため、直接感覚に訴える要素を退けました。一方、のちに登場する抽象絵画が純粋に絵の上にだけある色や形で構成されたのに対して、彼らはギターなどの楽器を始めとして、具体的なモチーフをもとに絵を描くことを最後まで止めませんでした。
しかし、いくら具体的なモチーフがあったとしても、「分析的キュビスム」の方法を突き詰めると対象は粉々、バラバラになり、何が描かれているのかわからなくなります。そうした現実との結びつきの希薄さに不満を持った二人は、バラバラにしたものを再度結びつけるような段階へと進みました。1912年から始まった「総合的キュビスム」です。
そこでは、以前は退けられた色彩や、具体的な素描が復活しました。また、画面に現実感を取り戻すため、既製品の壁紙や新聞紙などを貼り付ける「パピエ・コレ」という技法が生まれたことも画期的でした。「貼り付けられた紙」を意味するこの手法は、のちのダダやシュルレアリスムの作家たちが多用した「コラージュ」という方法論につながります。
「総合的キュビスム」の時期には、フアン・グリスという画家も運動の重要な担い手になりました。また、若い世代からキュビスムを発展的に展開させようとするさまざまな動向や人物が現れたのもこの時期の特徴です。そのなかには、イタリアの未来派や、のちに建築の巨匠となるル・コルビュジエらの「ピュリスム」、さらに、《階段を降りる裸体No.2》のようなキュビスム的な絵画からスタートし、その後、より概念的な仕事へ進んだマルセル・デュシャンもいました。
ピカソとブラックによる協働は、1914年に第一次世界大戦が勃発し、ブラックが戦地に赴いたことで終わってしまいます。しかし、感覚ではなく知覚を重視すること、遠近法とは異なる絵画にしかできない空間の探究、パピエ・コレに見られる既製品の利用など、キュビスムがその後の20世紀美術に残した視点や方法論は非常に重要なものでした。
杉原 環樹
1984年東京生まれ。武蔵野美術大学大学院美術専攻造形理論・美術史コース修了。出版社勤務を経て、現在は美術系雑誌や書籍を中心に、記事構成・インタビュー・執筆を行う。主な媒体に美術手帖、CINRA.NET、アーツカウンシル東京関連。編集協力として関わった書籍に、卯城竜太(Chim↑Pom)+松田修著『公の時代』(朝日出版社)など。
(この記事は2021/8/31にNewsletterで配信したものです)
PRODUCT INFO