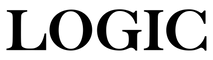LOGIC MAGAZINE Vol.19

LOGIC|SHARE
今、読者の皆さんと一緒に考えたいと感じた
ホットなトピック
今週末、LOGICが『CHOOSEBASE SHIBUYA』にてPOPUP STOREを出店。

LOGICは、今年9月に西武渋谷店にオープンしたメディア型OMOストアCHOOSEBASE SHIBUYA(チューズベース シブヤ)に12月11日(土)・12日(日)の期間限定のPOPUP STOREを出店します。
「CHOOSEBASE SHIBUYA」は、常に新しい出会いと学びのある購買体験を提供し、‟意味に出会い、意志をう”という次世代の店舗のあり方を提案するメディア型OMOストアで、6ヶ月毎に、未来に繋がる「テーマ」をひとつ立て、そのテーマを軸にブランドや内装やPRが入れ替わる仕組になっており、テーマを軸に、ブランドと消費者をマッチングする場として、従来の百貨店とは異なるコンセプトで運営されています。
今回、CHOOSEBASE SHIBUYAが目指す、思いや意味を知ることで共感が生まれ物を買う、共感軸の消費を大事にするという姿勢に大変共感し、出店することにいたしました。コンセプトやテーマに共感して来店される方々に改めてLOGICの思想を知っていただいたり、体験の場になればと考えています。
尚、期間中は代表の佐々木やLOGICのメンバーが店頭に立ちます。また、記念ノベルティやカフェチケット、限定のギフトラッピングサービスなどの購入特典も目白押しなので、週末はぜひお立ち寄りいただき気軽に声をかけてください。心よりお待ちしております。
出店概要
開催期間:2021年12月11日(土)〜12月12日(日)
営業時間 : 11:00 〜 21:00
販売店舗:西武渋谷店パーキング館 1F CHOOSEBASE SHIBUYA BASE B内 イベントスペース
住所 : 〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1
アクセス : https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/access_info/
購入特典:
①ご購入者様にもれなくロジックオリジナルの今治製ミニタオルをプレゼント。
②さらに、5,000円以上お買い上げの方に、施設内にあるTAILORED CAFE SHIBUYAのコーヒーが1杯無料で飲めるカフェチケットをプレゼントいたします(先着順・無くなり次第終了)
③ラッピングご希望の方には、サステナビリティに考慮した再生コットン製のオリジナルギフトバッグ(数量限定)を無料でサービス。
LOGIC | PEOPLE
第一線で活躍するプロフェッショナルの体験や知見から
パフォーマンスアップにつながるヒントを学ぶ。

019
株式会社TeaRoom
岩本宗涼氏
LOGIC MAGAZINE第19回インタビューにご登場いただくのは、「茶の湯文化×日本茶産業」の切り口でさまざまな事業を手がける株式会社TeaRoomの岩本宗涼氏です。2018年に同社を創業して以来、さまざまな企業やブランドとコラボレーションを実現している岩本さん。全2回でお届けする前編では、小学生の頃から慣れ親しんでいたお茶を事業化したきっかけや同社の取り組みについて尋ねました。(聞き手:LOGIC MAGAZINE編集部 佐々木、村上)
お茶文化をキリスト教のように
世界へ伝搬したい
ー岩本さんはどうしてお茶に魅せられたのでしょうか?
岩本:僕は小学4年生で茶道をはじめたのですが、みんな年齢とか身分とか関係なく接してくれるんですよ。9歳だろうが、60歳だろうが、学生だろうが、社長だろうが、茶室に入れば全員が同じ立場になれて、嫌なことがあっても茶室に行けばすべてを忘れて会話を楽しむことができる。それがすごく心地よくて。いつの間にか僕の居場所になっていました。
ーそれから起業に至ったのはどういったきっかけが?
岩本:最も大きかったのは、アメリカでの出来事でした。茶道家として講演を頼まれて訪れた際に現地の人から質問を受けたのですが、利休について尋ねられた次の瞬間には抹茶ラテのつくり方について教えてほしいと言われるんです。これが日本だったら、そんなアホな質問をするなとなるじゃないですか。
ー茶道家にそんな質問をするのは失礼だと一蹴されて終わりますよね。
岩本:でも、世界のお茶に対する認識ってそういう状況なんですよ。彼らも悪気があってそういう質問をしているわけではないし、むしろ興味があるからこそ積極的に質問をしてきてくれる。ここにチャンスがあると思いました。つまり、現代には“茶の湯文化”と“お茶産業”の両方をつなぐ担い手がいないわけです。
ー大きな溝ができているわけですね。
岩本:それにも明確な理由があって。というのも、茶室では「問答」と言って亭主とお客様との会話があるのですが、抹茶に関しては、お詰め(抹茶を製造したお茶屋さんの名前)とお茶銘(抹茶につけられた名前)の2つを聞くという流れがあって、それ以上の詳細を話すことはなかなかありません。しかも、先生もお茶がどういった工程を経てつくられているのかを知らないことがほとんどです。「これってどこでつくられているんですか?」と先生に聞いても「宇治産です」で終わってしまう。
ーでも、本当はどこかの農園で採れて、それをどこかの工場で加工して届けられているわけですよね。
岩本:そうです。一方で、生産側も「日本には茶道というすごい文化がある」というところで認識が止まっていて、双方が歩み寄る気配もない。だから、理解が深まらないわけです。でも、この溝は確実に埋められると思いました。というのも、僕は以前から「なぜこのお茶が高いのか」とか「なぜ竹製の茶筅(抹茶を点てる道具)を使うのか」とかをアメリカ人に対してロジカルに説明していたんです。実はこれができる人って日本国内でもほとんどいなくて。
ーだからこそ、分断をつなぐ役割を岩本さんが担おう、と。
岩本:でも、かつては文化と産業がつながっていたんですよ。僕らの会社がお茶を生産している本山という地域も、かつては徳川幕府が治めていた場所でした。徳川の将軍が「この茶がいい、これが好みだ、つくれ」と言って生産を農家に任せていたわけです。いつしかその状況がなくなって、文化と産業の分断が起きているのが今。お茶の価値は下がり続けて、産業としても成り立たなくなっています。
お茶だけで事業の成立が難しいからこその挑戦
ーそのなかで岩本さんがまず取り組まれたことは何だったのでしょうか?
岩本:生産の部分に取り組みました。そもそも現在の市場価値では、お茶だけで事業を支えることはすごく難しいんです。お茶で儲けているように見える企業の多くは、別の事業で生計を立てていることがほとんどで。商社におけるお茶の営業利益率は全体の2%程度だと言われています。たったそれだけの利益では、何もアクションを起こすことができません。だから、どんどん疲弊していく。そこで僕たちは、1社で事業を請け負うことははじめから諦めて、静岡市内で最も輸出をしている茶商と合弁で「THE CRAFT FARM」という農業法人をつくりました。そして、双方で研究開発費として予算を捻出して、成果が出ればグループ会社が茶葉を買うことでその利益も計上できるようにしたんです。
ー研究開発は具体的にどんなことを?
岩本:既存の業界慣習に囚われないマーケット目線での新規商品開発や、茶畑の「改植」と言ってお茶の新品種を植えています。ワインでたとえるとシャルドネのような高付加価値品を生み出そうとしていて。農業分野は保護が手厚く、行政機関もバックアップしてくれます。
ーリスクを分散すると同時に、利益を生み出す仕組みをつくったわけですね。
岩本:それだけではなく、行政の方々と連携して担い手がいなくなった農地を継承することにも取り組んでいます。それも農業法人をつくった理由のひとつでもあって。というのも、いきなり「譲ります」と言われても土地の状態が悪いとそれだけコストがかかってしまうじゃないですか。できるなら、「譲りたい」と言われたときにすぐに返事をして、ベストな状態で引き取りたいので、現地とのハブとなる媒介が必要でした。それが実現できたことで、地元への影響を拡大させながら、茶畑となる農地を拡大させることができています。
ーそれを農業法人で実現している、と。
岩本:あと、それに付随して工場も譲り受けました。静岡市に40年ほど使われていた工場があったのですが、区画整備の関係で移転再建しなければならなくなったんですね。ただ、それは公的理由があったので市が補助金を出す形で実施されました。そのときに機械などもすべて刷新して莫大な費用をかけたわけですが、40年前と比較してお茶の値段は4分の1に下落しているので、赤字経営が続いて経営破綻してしまったんです。とはいえ、市としては手間を投じて再建したこともあり、運営義務が発生していました。そこで運営者の募集がはじまったタイミングで手をあげたんです。現在は、数人のメンバーが現地に赴いて運営しています。
ー地方にいきなり足を運んでも歓迎されないことが多いと思うのですが、実際はどうでしたか?
岩本:今でこそすごく良好な関係を築けていますが、最初は拒絶反応もありました。20代そこそこの若造が都会から急に移住してきたら、そういう反応になりますよね。
ーどうやって親交を深めたのでしょうか?
岩本:集会所に足を運んで、生産者さんのつくった茶葉がどんな製品になるのかをプレゼンテーションしました。たとえば、茶葉を使ってクラフトジンを製造したのですが、それを紹介してみると「自分たちのお茶がお酒になるなんて知らなかったよ」と喜んでくださって。そういう繰り返しのなかで賛同してくれる方が増えていきました。しかも生産部分にアプローチしていることで、業界内でもポジティブに受け止めてくださる方々が多くて。これがマーケティングの部分だけ取り組んでいたら、ここまでの結果を出すことは難しかったと思います。
複数の企業と協業することで生まれるシナジー
ー岩本さんのように複数の企業と関わり合いながら事業を推進していくスタイルはスタートアップのなかでは珍しいですよね。
岩本:それにはいくつか理由があって。ひとつは自分たちの会社だけで事業を進めていても業界全体が潤うことにはならないんですよね。それよりも人々とお茶のタッチポイントを増やした方がよくて。たとえば、完全な自動運転が実現して人間が車を運転する必要がなくなったら、車で移動しながらお茶を満喫することができますよね。また、宇宙空間で過ごすようになったら宇宙におけるアフターヌーンティーの価値について議論しないといけないなと思うわけです。そうしたら、僕たちだけの事業として留めるのではなく、いろんな企業と協業して彼らのアセットを使ったアップセルやクロスセル、新規事業を一緒に立ち上げていく方がスピード感を持って展開できるじゃないですか。
ー常に業界のことを考えて行動しているわけですね。
岩本:言い方を変えたら、それくらいのことをしないとお茶業界は復活しないと思っているんですよね。あと、僕らの会社では理念として「お茶で対立のない優しい世界をつくる」を掲げていることにもつながるのですが、物事に境界線を引くことにあまり価値を見出していなくて。昔から世代を超えてコミュニケーションを取っていたことだったり、過去にアメリカに留学していたときに国籍を超えて共通の話題で盛り上がったりしたことが経験としてあるからだと思うんですけど、対立することに意味があるとはどうしても考えられないんですよ。
ーむしろ、境界線を取り払って有機的に結びついていきたい、と。
岩本:それは昔の農家たちの知恵から学んだことでもあって。宇治の茶農家さんのなかにお米をつくっているケースがあるのですが、それはお茶を収穫する前に藁で日光を遮断するために必要だから取り組んでいることなんですね。
ーそれはどういった理由から行うのでしょうか?
岩本:お茶の樹って太陽を遮断すると、光を求めて上に伸びていくんです。そうすると枝の丈が揃うので収穫しやすくなります。また、日光を浴びることで起こる光合成を抑えて、旨み成分であるテアニンを増やすことにもつながるんです。それをかつては有機の藁を使って取り組んでいたのですが、藁をつくる生産者が減ってきたことをきっかけに茶農家さんたちが自分たちでお米をつくるようになったらしいんです。そうするとお米もできるので、それを玄米にして、高値で取引きできない二番茶や三番茶とブレンドして玄米茶にして自分たちで売ってしまう。そして、使い終わった藁は肥料にするんです。それを毎年繰り返すと。
ー見事な循環が成立しているんですね。
岩本:僕も「できすぎじゃない?」と思ったのですが、これこそ百姓の暮らしなんですよね。いろんなことに取り組むからこそ、接点が生まれてくる。それが日本のものづくりなんでしょうね。それを組織としても実践しないといけないと思いました。実は農業法人を「THE CRAFT FARM」にしたのも、お茶を焙煎する機械がコーヒーやカカオを焙煎するものと同じだからだったんです。でも、お茶とコーヒーでは焙煎に関する知見に天と地ほどの差があるわけじゃないですか。
ー同じ焙煎機を使っているのに文化が違うわけですね。
岩本:コーヒーだったら、焙煎に対して等級がつけられて、浅煎り、中煎り、深煎りと分けられているし、そのうえで火入れに関する研究も進んでいます。でも、お茶だと緑茶を焙煎してほうじ茶にするくらいしかバリエーションがない。それが不思議で仕方なかったんですけど、さっき話したように別のものに応用できるんだったら、それぞれの知見を合わせてしまったほうがより良いものができると思うんです。それを事業にも転換して、さまざまな人や企業を巻き込んで事業にしています。
(次号、後編へ続く)
LOGIC | CULTURE
教養としてのカルチャーを楽しみながら学ぶ。

illustration:うえむらのぶこ
「ビジネス映画学」第1回
『ウルフ・オブ・ウォールストリート』
身も蓋もない話ですが、ビジネスの根本的な目的はお金を稼ぐことにあります。もちろん、やりがいや社会的意義も大事だとは思いますが、お金を稼げないのであればビジネスとしては成立しないことは言うまでもありません。では、ビジネスマンとして、日本を含む資本主義社会で効率的にお金を稼ぐにはどうしたらいいでしょうか。そんなことを考えるときいろんな意味で参考になるのが、マーティン・スコセッシ監督、レオナルド・ディカプリオ主演の怪作『ウルフ・オブ・ウォールストリート』です。
本作の主人公はディカプリオ演じるジョーダン・ベルフォートです。ジョーダンは実在する人物で、本作も彼の回想録『ウォール街狂乱日記 「狼」と呼ばれた私のヤバすぎる人生』が原作になっています。22歳で結婚したジョーダンが、金持ちになることを夢見てウォール街の投資銀行LFロスチャイルドに入社するところから、物語は幕を開けます。そこで上司ハンナにブローカーとしてのイロハを叩き込まれるのですが、半年かけて証券外務員の資格を取って出社したその日に、「ブラックマンデー」(1987年に起こった世界的株価大暴落)で会社は倒産。失業したジョーダンは、郊外のちっぽけな証券会社に就職することになります。ところが、その労働者階級向けにペニー株(安すぎてナスダックに上場できない数)を仲介するその会社は、手数料が50%だというではないですか。ロスチャイルド社では1%だったのに! これに発奮されられたジョーダンは、ウォール街仕込みの口車で顧客を魅了し、たちまち稼ぎ頭となるのでした。
その後、ジョーダンはゴロツキたちを集めてガレージでストラットン・オークモント社を設立し、ターゲットを労働者階級から富裕層へと変えます。これが功を奏して会社は急成長を遂げ、オフィスもウォール街に構えることになり、ついには一流ビジネス雑誌『フォーブス』の取材まで受けることにもなります。この取材はジョーダンを「ウルフ」と呼び、そのやり口をディスりまくるものだったのですが、むしろいい宣伝になり社員は急増。ストラットン・オークモント社はウォール街に比類なき地位を築くことになるのでした。
ジョーダンから得られるビジネスのヒントは、主として2つあるように思われます。まずは、需要創出の手法。あるとき、ジョーダンは聴衆にビジネスのなんたるかを教えるために、何の変哲もない1本のペンを差し出し、「これを俺に売ってみろ」と言います。聴衆の多くは、「これは非常にいいペンなんです」とありがちな売り文句を並べるのですが、そんなんじゃ誰もが家にひとつは持っているだろうペンを売ることなどできません。では、どうすれはいいのでしょうか。実はジョーダンは会社を設立する際、同じことをゴロツキたちにも問うているのですが、その中の1人が“正解”を出しています。彼は紙を差し出し、別のメンバーに「ここに名前を書いてくれ」と言うのです。すると、言われた方は戸惑いに気味にこう言わざるをえません。「ペンはあるか?」。ジョーダンはこのやりとりを高く評価し、需要はこうして作り出すのだと語ります。つまり、今この瞬間に必要だと思わせたらこっちのもんというわけです。
やや変化球的な手法とは言え、ここまでならビジネスの基本と思われるかもしれません。ただ、前述の物語内容を頭に入れておけば明らかな通り、ジョーダンが売る株は決して優良なものではなく、あえて言うならクズ株です。ペンより役に立たないかもしれません。需要の枠は確保できたとして、その商品にクズを当て込んで売りぬくにはどうすればいいか。これがヒントの2点目になるのですが、信頼感を身にまとうことに他なりません。少なくともジョーダンに限っては、それは株取引に関する知識や実績などとは無縁です。実際、初期メンバーは株のことなどまったく知らないゴロツキなんですから。それ以上にジョーダンが重視するのは、信頼できそうな会社名とロゴを掲げ、信頼できそうな口調を身に着け、ウォール街にオフィスを構え、たとえ批判記事であっても一流誌に掲載されたということを最大限の宣伝にしてしまう……といったこと。こうして形作られた信頼感こそが、顧客を購買へと進ませる後押しになるというわけです。
以上がジョーダン流のビジネスにおけるお金の稼ぎ方です。「いやいや、ジョーダンのやっていることって詐欺まがいなんじゃないか?」と思う向きもあるでしょう。最終的にジョーダンは数え切れない罪状で牢獄に収監されてしまうのですから、それはそのとおりです。しかし、彼らは資本主義というゲームのルールを熟知し、それを極端な方法でプレイしたに過ぎないという見方もできるのではないでしょうか。そして、この社会に生きている以上、我々もこのゲームに参加しているし、参加せざるをえません。重要なのは、それを頭に入れたうえで、自分はどうするかと考えることでしょう。よりクリーンなビジネスを目指すのか否か、要するにジョーダンを教師とするか反面教師とするか。それはあなた次第です。
鍵和田 啓介
1988年生まれ、ライター。映画批評家であり、「爆音映画祭」のディレクターである樋口泰人氏に誘われ、大学時代よりライター活動を開始。現在は、『POPEYE』『BRUTUS』などの雑誌を中心に、さまざまな記事を執筆している。
(この記事は2021/12/9にNewsletterで配信したものです)