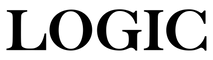LOGIC MAGAZINE Vol.20

LOGIC|SHARE
今、読者の皆さんと一緒に考えたいと感じた
ホットなトピック
年末のご挨拶と次回バージョン経過報告
本年もLOGICとLOGIC MAGAZINEをご愛顧いただき、誠にありがとうございました。おかげさまでこの1年、少しずつではありますがブランドとして一歩一歩前進することができました。取り扱い店舗やPOPUPへのお誘いが増えたり、当初メンズスキンケアとしてリリースしたLOGICも、今では性別を問わず愛用いただいたり、大切なひとへのギフトとして選んでいただけることも増えてきました。
そして、来年はいよいよ新バージョンへのアップデートをいたします。アップデートに関してはひとつお詫びがあります。今夏にサンプルモニターの募集させていただきましたが、当初の予定より遅れており、次回バージョンのサンプル作成にもう少しお時間をいただくことになりそうで、サンプルは来年2月頃、リリースは春〜初夏頃を予定しています。モニター希望者の方や、次回バージョンを楽しみにしている皆様にはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
試作中のサンプル。エアゾールタイプの見直しも視野にいれて改良中。
現在の進捗ですが、先日当記事でお伝えした香りに加えて、洗顔・化粧水共にある程度バルク(中身)は定まってはきているなかで、使用感の微調整、新しい処方の検証をおこなっております。特にミスト化粧水に関しては、現バージョンとかなり変わったものとなる見込みです。時間がかかった分、より進化を実感してもらえるように尽力してまいりますので、ぜひご期待ください!
来年も皆様にとってより魅力を感じるブランドに育てて参りますので、どうかよろしくお願い申し上げます。それでは、良いお年をお迎えください。(佐々木智也)
LOGIC | PEOPLE
第一線で活躍するプロフェッショナルの体験や知見から
パフォーマンスアップにつながるヒントを学ぶ。

020
株式会社TeaRoom
岩本宗涼氏
LOGIC MAGAZINE第20回インタビューにご登場いただくのは、前回に続き「茶の湯文化×日本茶産業」の切り口でさまざまな事業を手がける株式会社TeaRoomの岩本宗涼氏です。2018年に同社を創業して以来、さまざまな企業やブランドとコラボレーションを実現している岩本さん。後編では、岩本さんがこれから取り組みたいことについて伺いました。(聞き手:LOGIC MAGAZINE編集部 佐々木、村上)
茶道の精神を世界中へ
そこからはじまる新たな茶の湯文化
ーお茶の価値を向上させていくにあたり、岩本さんはどのようなことに取り組もうと考えているのでしょうか?
岩本:前提として、生産者側から新たなアイデアが生まれにくいことは僕たちも理解していて。というのも、静岡の農業法人・THE CRAFT FARMはTeaRoomの創業メンバーが現地に移住して運営しているのですが、生活や思考が段々と農家に近づいていて。それで何が起こるかというと、つくることに必死になるあまりアイデアが限定化されていってしまいがちなんですよ。そのなかでは、ウェルビーイングとかSDGsとか言っても理解できないんです。だから、既存の業界に期待するんじゃなくて、自分たちで成功モデルをつくって拡げないといけないよねという結論になりました。そのためには、茶の湯文化がいかに社会と接点があるかを認知させなければいけません。茶人が当たり前としている考え方をもっと普及していかないと、そもそもの母集団が増えないなと。そこでモデルにしたいのがキリスト教なんです。
ーキリスト教とお茶がどのように結びつくのでしょうか?
岩本:キリスト教の思想って全世界に普及しているじゃないですか。その思想が土台としてあるからこそ、人々は教会に行くし、聖書も読むし、十字架も身につける。これって見方を変えるとものすごく強いコンテンツだと思うんですよ。僕らにとっての茶室と茶碗と茶筅みたいなものなので。茶の湯文化を広げていくためにはとても重要な視点だと感じます。そのうえで切り口にしたいのが“道の精神”なんです。
ー茶道ですか?
岩本:はい。アフタヌーンティーをはじめとする喫茶文化は世界中で多用に広がっていますが、そのほとんどがエンターテインメントと結びついて商業化しているんですね。ところが日本では、“道”の文化として昇華され、生き方を学ぶ手段になっています。この茶道の考え方を世界中の喫茶文化に付与していくことで、新しい茶の湯文化が開拓できるのではないかと考えています。
ーとはいえ、文化が根づくまでには多くの時間が必要となりますよね。
岩本:だから、TeaRoomでは、数十年先も見据えた長期計画を練っています。それくらいの月日が経つと世代が一世代、二世代と切り替わっていくので、その時代を生きる人の価値観が徐々に変わっていくことで、市場をリプレイスできると思うんですよ。たとえば、缶のお茶が発売されたのは1981年のことですが、それから40年後の2021年にはほとんど見かけなくなり、その多くはペットボトルに切り替わっているじゃないですか。
ー同じような変化が起こるんじゃないか、と?
岩本:はい。とはいえ、お茶が市場で消費されている形態の多くははペットボトルなどの清涼飲料水なので、その需要は残り続けるはず。それ以外は冠婚葬祭用であることが多いので、実はスペシャリティなお茶はほとんど流通していないんです。
ーそれはどういった理由があるのでしょうか?
岩本:採算が取れないからですね。たとえば、1kg1万円のお茶を20kg売ったとしても20万円にしかならないし、そのための品種をつくれる農家さんってほんのひと握りしかいなくて。逆に1tとか10tとか大量に用意しようとすると大規模農園でしか実現できないんですけど、それくらいの規模でお茶をつくっているところは清涼飲料水用のお茶をつくっているので、スペシャリティなお茶に取り組むメリットがあんまりないんですね。だから、なかなか取り組むことがないんです。でも、お茶の消費のされ方のリプレイスが起きれば、その状況も変えていけるんじゃないかなと考えています。
他社が関わることでお茶の価値は変わる
ーその変化はすでに起きはじめているのでしょうか?
岩本:そうですね。現在でもお茶に投資する企業が増えているんですよ。しかも、不動産会社とか航空会社とか主力とする事業がほかにある企業から声をかけていただくことが多くて。これは僕たちにとってはすごくポジティブな変化で。たとえば、化粧品メーカーから「お茶のこの成分を活用した化粧品を開発したい」と声がかかったら、これまでと違う茶葉の販路ができるわけじゃないですか。現状でもエナジードリンクやGABAチョコレート、猫の缶詰などにお茶由来の成分が入っていて。そういう意味では、すごく使い勝手が良い。しかも、各社がすでに持っている販路を通してお茶の消費が起こるので、生活者の体験として蓄えられていくはずなんですよ。それと同時に、我々は企業の担当者を茶事やお茶の稽古にお呼びして文化性を育んでいく。そうやって企業と生活者の両方にアプローチしていけば、お茶の価値を上げていけるんじゃないかなと考えています。
ーちなみに、自分たちで新たなブランドを立ち上げることは考えていないのでしょうか?
岩本:おそらく事業の成長スピードと業界の衰退スピードが合わないので、結局生産者が疲弊してしまい、原料がなくなってしまうと思うんですよね。それならば、外部の協力を得たほうがいいだろうなというのが現状の答えになります。ただ、将来的な可能性はあると思います。
お茶を通してさまざまな境界を溶かしていく
ーここまでいろんな企業の力を借りながら取り組むスタートアップも珍しいですよね。
岩本:そもそもお茶って境界を溶かすものだと思うんですね。全然関わり合いがない人でもお茶を飲むという行為を通じて仲良くなれるし、何も喋らなくてもなんとなく時間を共有することができるじゃないですか。協業するのも似たようなもので、お茶を通じてそれぞれの業界が持っている知恵や知見を集めていくことで新たな市場が生まれると思うんですよ。しかも、各業界には僕たちではリーチできないお客さんが大勢いるので、お茶の需要も多様化できるはず。
ーこれから先、多様な茶の湯文化が花開いてほしいですね。
岩本:茶の湯文化は世界で通じると思うので、それこそ各国の首脳陣とかロイヤルファミリーとかも訴求できると思うんですよ。近い将来、G20に呼ばれて茶人として紹介されるようなミラクルを起こしたいですね。
______________
岩本宗涼さんのパフォーマンスアップのためのルーティーン
「まずは体験してみる」
世の中には時間をかけないとわかるようにならないものがあると思っていて、そういうものほどわからないまま体験するようにしています。たとえば、能は何回観てもよく理解できないんですけど、もしかしたら5年くらい経ったら理解できるようになるかもしれない。そういう瞬間が訪れることを楽しみにしています。
「2日以上休みが取れそうだったら旅行する」
土日って何も予定を立てないとダラダラして終わってしまうことが多くて、すごくもったいないと思ったんですね。それで最近は、思い切って遠出するようにしていて。金曜日の夜に出発すると、土曜日と日曜日を使ってけっこういろんなところを観て回れるので、良いリフレッシュになるんですよ。
「お茶を入れるときに全員分用意する」
僕らの会社では、お茶を入れるときに自分の分だけでなく、その場にいる他のメンバーのものも用意するという習慣があります。でも、これって誰かが決めたことではなくて。自然発生的に生まれたのが面白いなと思っています。
岩本宗涼さんのおすすめのワークツール
「茶器」
僕の仕事道具です。この仕事をするようになってから数が倍増しているのですが、その多くが知人や後援者から譲り受けたもので。僕も誰かに引き継ぐ使命を背負っているのだなと思うと身が引き締まりますね。
LOGIC | CULTURE
教養としてのカルチャーを楽しみながら学ぶ。

「アートのロジック」第7回
『ポップ・アート』
知ってるようで知らないアートを読み解く連載「アートのロジック」。第7回は、20世紀に一世風靡し、今でも至るところにその影響を残すポップ・アートについて。多くの芸術家を輩出したこのムーヴメントについて、その成り立ちから解説します。
ポップ・アートは、第二次世界大戦後の1950年代半ばのイギリスで萌芽し、1960年代のアメリカで爆発的に華開いた芸術潮流です。大量生産品やマスメディアのイメージを作品に積極的に取り入れるその動きは、「低俗な大衆文化と一線を画すのが芸術である」という従来の常識を打ち破り、アートを人々の日常や現代社会のリアルへと接近させました。
1950年代、戦勝国アメリカでは経済が発展、消費社会化が加速します。アメリカから届く新しい生活様式は世界の憧れの的でした。それは同じ戦勝国のイギリスでも同様で、この頃そうした新しい文化に反応して雑誌や広告のイメージを作品に使う若者が現れました。
そうしたなか、批評家ローレンス・アロウェイの周辺で、その新しい作品の感覚を指す言葉として「ポップ・アート」が使われ始めます。リチャード・ハミルトンの《一体何が今日の家庭をこれほどに変え、魅力あるものにしているのか》(1956年)は、アメリカ型の消費文化に反応して作られた記念碑的なコラージュ作品で、画面には「pop」の文字が刻まれています。
一方、1950年代のアメリカにも、のちに隆盛するポップ・アートの表現を先取りするような動きがありました。それが、ジャスパー・ジョーンズとロバート・ラウシェンバーグを代表とする「ネオダダ」です。二人は日用品や身近な記号、印刷物、都市が生み出したジャンク(廃品)のようなものを作品に大胆に取り入れました。
「ポップ・アート」が明確に台頭するのは1960年代です。1962年にニューヨークの画廊で開催された「ニュー・リアリスツ」展は、既製品(レディメイド)やマスメディアのイメージを利用した作品群が並んで大きな注目を集めた、ひとつの画期となる展示でした。
この「ポップ・アート」を代表するアーティストと言えば、同展にも参加していたロイ・リキテンスタインとアンディ・ウォーホルの二人でしょう。
リキテンスタインは1950年代に抽象表現主義風の作品を制作していましたが、自分の子どもと触れ合うなかで絵画としての漫画の可能性を感じ、漫画の一コマを拡大して絵画を描き始めます。釣りをするミッキーマウスたちを描いた1961年の《Look Mickey》はその初期の代表作。彼のこうした方法論は、当初は美術界から批判されました。
63年頃からは《ヘアリボンの少女》(1965年)のような、大衆漫画のステレオタイプなヒロイン像を描く「ラブ・コミック」シリーズを開始します。恋愛ドラマの登場人物である女性たちは、涙を流したり、嘆いたりと、エモーショナルな表情を見せていますが、それらを漫画特有の太い輪郭線や、写真製版の特徴であるドットを強調して描くリキテンスタインの態度から、「これは所詮、印刷物に過ぎない」という冷めた眼差しも感じます。
こうした漫画をモチーフとした作品群は、いくつかの基本的な色によって、フラットさを強調して描れました。そこからは、通俗的でありふれたイメージを扱いつつも、リキテンスタインがそれらをピエト・モンドリアンなどの近代絵画の延長線上にあるものとして描いていたことが感じられます。実際、彼はその後、モネやピカソといった近代の巨匠の作品や、抽象表現主義の代名詞である「ブラッシュ・ストローク」(筆跡)などを自身のスタイルで描き直すなど、美術史に対する自己言及的な作品も多く残しました。
一方のウォーホルは、ポップアートのみならず、20世紀最大のアート界のスターの一人と言っても過言ではないでしょう。シルクスクリーンという版画の技法で制作されたマリリン・モンローやキャンベルスープ缶のイメージはあまりにも有名です。
ウォーホルは、1950年代半ばにはすでに商業デザイナー・イラストレーターとして有名な存在でした。しかし、ファインアートに転身。1960年代前半に、アメリカ的な大量生産の代表格であるコカ・コーラの瓶やキャンベルスープ缶、マリリン・モンローやエルヴィス・プレスリーらポップスターのイメージを利用した作品で時代の寵児となりました。
一枚のマリリン・モンローの写真をもとに、色違いの作品を何枚も反復的に制作するその手法は、商品としてのキャンベルスープ缶がラベルに記された味の違いのみで区別されつつ、大量生産されるのと似て、資本主義のダイナミズムやその記号性を突きつけます。その作品群は、当時加速していた消費社会化のリアリティを見事に捉えていたのです。
同時に、このマリリン・モンローの作品は、じつは彼女の突然の死を契機に作られました。ウォーホルにはほかにも、自動車事故や電気椅子の写真を用いた「死と惨劇」というシリーズもあります。こうした死のイメージの使用には、死すらも表層化・記号化する社会への批評性も感じさせますが、ウォーホル自身によるそうしたイメージの再生産は、死の軽さへの肯定とも捉えられるかもしれません。
「表面」や「表層」に留まろうとするウォーホルの姿勢は徹底したもので、彼は「アンディ・ウォーホルについて知りたいなら、表面だけを見ればいい」という名言も残しています。芸術論に付き物の「本質」「奥深さ」「作家の内面」などを一蹴し、ただ作品の表面だけを見てくれ、自分はそこにしかない(「中身」なんかない)と言うわけです。
ウォーホルは自身のスタジオを「ファクトリー」(工場)と呼び、そこで一連の作品をアシスタントと流れ作業で、まさに機械的に「生産」しました。また、ファクトリーは著名人やアーティストの社交場ともなり、そうした交流からウォーホルはロックバンド「ヴェルヴェット・アンダーグラウンド」のプロデュースを行います。バナナが描かれたデビューアルバムのジャケットは誰もが一度は目にしたことがあるでしょう。いまでも彼の作り出したイメージはTシャツなどに印刷され、大量に世の中に放たれています。
テレビが本格的に普及し始めた当時、自身もマスメディアに頻繁に登場し、その影響力を活用した点も画期的でした。ウォーホルのこうした振る舞いは、人々が「アーティスト」というものに対して抱くイメージを大きく変えたと言えます。
「高尚」で「奥深い」とされてきた芸術に対し、「低俗」で「くだらない」とされてきた大衆文化や消費社会のリアリティを突きつけたポップ・アート。それは、見た目の軽やかさに反して、従来の芸術の「神話」を無効化する強烈な批評性を帯びていたのです。
杉原 環樹
1984年東京生まれ。武蔵野美術大学大学院美術専攻造形理論・美術史コース修了。出版社勤務を経て、現在は美術系雑誌や書籍を中心に、記事構成・インタビュー・執筆を行う。主な媒体に美術手帖、CINRA.NET、アーツカウンシル東京関連。編集協力として関わった書籍に、卯城竜太(Chim↑Pom)+松田修著『公の時代』(朝日出版社)など。
(この記事は2021/12/30にNewsletterで配信したものです)