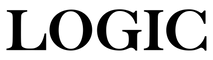LOGIC MAGAZINE Vol.22

LOGIC|SHARE
今、読者の皆さんと一緒に考えたいと感じた
ホットなトピック
3/12、LOGICが広尾『EAT PLAY WORKS』にPOPUP STOREを出店。

LOGICは、食とウェルネスとワークカルチャーが融合した複合施設『EAT PLAY WORKS』にて3月12日(土)に開催されるホワイトデースペシャルイベントにPOPUP STOREを出店します。
今回のイベントは、主に男性が心身ともにより健やかに生きていくためのヒントを詰めこんだウェルネスイベントです。男性ならではの体の悩みは、パートナーにとっても大切な問題。例えば妊活や性の問題など、なかなかパートナーと話し合えないテーマについて、気軽に楽しく理解を深めていただくため、「ヘルスケア」に特化したゲストを招待し、トークショーを開催します。
そのほかにも、LOGICをはじめ様々なメンズスキンケア用品やライフスタイル雑貨の販売、サステナブルブランドの展示会、廃材を使ったジュエリー制作やヨガ体験なども用意しております。
尚、期間中は代表の佐々木が店頭に立ちます。また、限定のギフトラッピングサービスなどの購入特典ありますので、週末はぜひお立ち寄りいただき気軽に声をかけてください。心よりお待ちしております。

イベント概要
開催日程:2021年3月12日(土)
営業時間:11:00 〜 19:00
販売店舗:EAT PLAY WORKS 3F・4F LOUNGE
住所 : 東京都渋谷区広尾 5-4-16
※東京メトロ日比谷線広尾駅より徒歩1分
アクセス : https://eatplayworks.com/location/
購入特典:
①ご購入者様にもれなくロジックオリジナルの今治製ミニタオルをプレゼント。
②ラッピングご希望の方には、サステナビリティに考慮した再生コットン製のオリジナルギフトバッグ(数量限定)を無料でサービス。
LOGIC | PEOPLE
第一線で活躍するプロフェッショナルの体験や知見から
パフォーマンスアップにつながるヒントを学ぶ。

022
THE株式会社
米津雄介氏
LOGIC MAGAZINE第22回インタビューにご登場いただくのは、「これこそは」と思える定番の一品をつくるブランド「THE」を展開するTHE株式会社の米津雄介氏です。大手文具メーカーで商品開発に従事していた米津氏が、THEに参画したのは2012年のこと。つまり2022年は、米津さんにとって節目の年というわけです。この長い月日のなかでどのような変化があったのでしょうか。(聞き手:LOGIC MAGAZINE編集部 佐々木、村上)
「定番をつくる」を
10年続けて気づいたこと
ー米津さんがTHEに参画してから10年の月日が経ちました。今でも夢中になれている理由は何だと思いますか?
米津:僕は自分の力を試したいとか、もっとお金を稼ぎたいとか、そういう欲はまったくないんですけど、「社会がもっとこうだったらいいのに」という理想は強くあって。それが実現できていないから続けてられているのかもしれません。
ー自分が納得したい気持ちが強いのでしょうか。
米津:そうだと思います。文具メーカーにいたとき、僕は企画職に就いていたのですが、ネタがないなかでネタをつくらないといけないことがとにかく辛かったんです。文具店は売上を伸ばしたいからどんどん新しい商品を打ち出したいわけじゃないですか。営業担当者からしてみたら新しいネタがほしいのは当然で、その皺寄せが僕らのところにやってくる。そうすると「差別化」という名のもとに“良いモノ”ではなく“ほかと違うモノ”の価値が優先されていくわけです。でも、本当に良い商品だったらみんな真似したいし、それによってコモディティ化していくのが健全だと思うんです。
ーだからこそ、THEでは定番となる商品を生み出すことに注力していると思うのですが、定番って経年とともに変化していきますよね。そのときどきの趣味嗜好によっても変わるというか。
米津:変わりますし、変わっていくべきものだと思っています。僕たちがものづくりをするうえで心がけているのは懐古主義にならないことなんですね。たとえばLevi'sの501はジーンズの定番ですし、僕たちの理想の姿として提示する機会も多いのですが、すべてにおいて最適なのかと言われたらちょっと疑問が残るというか。
ー現在の価値に照らし合わせてみると、違うなと感じる側面がありそうですよね。
米津:僕たちは「定番をつくる」というコンセプトを掲げているのですが、それは(未来の)という枕があって成立する言葉でもあって。10年後20年後の定番をつくるという未来軸で考えているんですね。だから、常に商品のアップデートを重ねているし、世の中のニーズが多様化しているなかで自分たちがどういう姿勢でいるべきかは常に考えています。
ーそのバランスってすごく難しいですよね。自分たちの理想を追求したい気持ちがある一方で、世の中に求められないものをつくってもしょうがないですし。
米津:芸能人のゴシップが話題になる度に、週刊誌が「だって、世の中が求めているじゃん」って語るじゃないですか。僕、あの姿勢がものすごく嫌いで。何かをつくって世の中に出す行為って、届ける相手に新たな価値感を築かせるきっかけを与えるものである必要があると思うんです。求められたからやるというのは、あんまり意味がないんじゃないかなって。
ーその人にない価値観を気づかせるっていいですね。
米津:自分がほしいものを見つけるのって口で言うほど簡単ではないんですよね。だから、アンケートとかもあんまり良い方法だと思わなくて。これは僕自身も経験があるのですが、何かしら良いことを言おうとするから、たった1しか考えていないことを10に膨らませて書いてしまう傾向が強くなるじゃないですか。それもn=1として残ることになってしまうので、それで本当にニーズがわかるのかなと思うことがあります。
セレクトショップとしての機能をいかに持続できるか
ーこの10年で実現できたことはどのようなものがあるのでしょうか。
米津:これは僕たちだけの力で実現できたことではないですが、上質でしっかりしたものを使うという価値感がこの10年で市民権を得るようになったと思います。自分たちのことに限定すると、セレクトショップとしての機能を保ったまま経営を続けられていることでしょうか。餅は餅屋だと思いつつ、お客さんからすると専業ブランドって買い物のしにくさがあって、だからこそセレクトショップが必要とされていると思うんです。ただ、純粋なセレクトショップって都心であればあるほど経営が難しくて。
ー確かに純粋なセレクトショップって都心では減っていますよね。賃料がネックになっていると思うのですが。それに伴って有名バイヤーや店長の影響力も落ちている気がします。目利きとしての価値がなくなってきているというか。
米津:そうしたセレクトショップの目利きとしての役割を補完しているのがYouTubeであり、Instagramのインフルエンサーだと思うんですよ。あと、地方にも面白いセレクトショップが増えている気がします。どうしても利益を優先しようとすると、オリジナル商品を増やした方がいいんです。でも、それが果たしてお客さんのためになるかというと違う気がしていて。だから、THE SHOPではオリジナル商品とセレクト商品の割合を変えないようにしています。それは頑張れているのかなと。
ー逆に実現できていないことはありますか?
米津:まだまだ「最適とは何か」というところまできちんと世の中に伝えられていないと思うんですよね。僕たちにとっての最適が何かというと、経済とか文化とか環境とかをしっかり潤して生きていけるツールを提供していくことなんですけど、それを世界中にあまねく届けたいかというと、そこまではイメージできてなくて。毎年1月になると事業計画を練り直すのですが、そのときにすごく考えます。けっこう長い年月を費やして事業に取り組んできたつもりなんですけど、まだまだ先が見えないですね(笑)。
ー登山みたいなものですよね。
米津:そうそう。あそこが頂上だと思っていたら、もっと高い場所があったみたいなことってすごく多くて。それは歩みをはじめたからわかったことでもあるんですけど。
ーこれから取り組みたいと考えていることはありますか。
米津:僕は、大学生だった頃に指導していただいた益田文和さんというインダストリアルデザイナーに影響を受けて今でも仕事をしているんですね。益田先生は20年以上も前に「サステナブルデザイン」を提唱しているすごい方なんですが、その影響を受けながら持続可能性を探ってブランド経営をしていくと、物量的なインパクトを出さないと地球には貢献できないと思って。そうすると、僕たちの規模の会社ができることって、思想をどう世の中に共有していくかだと思うんです。セレクトショップの話もそうですけど、「あそこがうまくできているんだったら、うちでもできるんじゃない」と思わせることが重要で。その発信をもっと強くしていきたいと考えています。
______________
米津雄介さんのパフォーマンスアップのためのルーティーン
「アウトドアスポーツを楽しむ」
結婚前は毎週のように出かけていたのですが、結婚してからは2週に1度に頻度を落として楽しんでいます。冬はバックカントリースキー、春夏は源流釣行、夏はサーフィン、あとはときどきマウンテンバイクなんかも。場合によっては命の危険にさらされる可能性があるので、本来であれば経営者は避けるべきかもしれません(笑)。ただ、そこまでしてアウトドアスポーツに取り組んでいる理由はふたつあって。ひとつは雑念を捨てられるから。経営ってさまざまなことを同時に進めないといけないので、何かに集中できる瞬間ってなかなかないんですよね。だから、アウトドアスポーツを楽しむことが良いリフレッシュになっている気がします。もうひとつは自然に対する畏敬の念を感じられるから。自然って自分ではどうすることもできない場面があるんですよ。しかも、気候を勉強するとあらゆる物事がつながっていることに気づけるんです。雪なんてここ5年くらいで降り方が明らかに変わっているし、雪崩の発生も増えていて。そういうことをリアルに感じることができるんです。あと、経営は辛いことの連続なので精神的に壊れてしまう起業家も少なくないのですが、幸いなことに僕はメンタルをやられたり、体調を大きく崩したりした経験がなくて。もしかしたら自然の脅威に晒されることでメンタル的に強くなれているのかもしれません。
米津雄介さんのおすすめのワークツール
「THE LINEN SHIRTS」
もともと「THE SHIRTS」というコットン生地でつくったシャツのシリーズがあるのですが、生地が厚いぶん夏だとやや着づらかったんですね。そこで通気性に優れたシャツをつくろうと思ってリネン生地のシャツをつくりました。リネンの繊維は中央が空洞の形状になっているので速乾性が高く、汗や湿気をすばやく外に放出してくれるので、夏でもさらっと着られます。しかも、寒い時期は繊維の空洞に空気が留まるのでけっこう暖かいんですよ。通年で使用できるのでかなり重宝しています。
「AirPods」
もうこれがないと生活できないレベルになってしまいましたね。ノイズキャンセリング機能が付いているBluetoothイヤホンという能力値と、細かなところまでこだわり抜いたプロダクトとしての完成度、その両方が高いレベルで維持されているのが本当にすごいなと。欲を言えば、もう少し充電が持てば最高なんですけど(笑)。
LOGIC | CULTURE
教養としてのカルチャーを楽しみながら学ぶ。

「アートのロジック」第8回
『アーツ・アンド・クラフツ』
知ってるようで知らないアートを読み解く連載「アートのロジック」。第8回は、19世紀後半のイギリスで興った『アーツ・アンド・クラフツ』です。ある種の社会運動にまで発展したこの芸術運動は、私たちの生活にどのような影響を及ぼしたのでしょうか。
アーツ・アンド・クラフツ運動は、19世紀後半のイギリスで興った造形運動です。産業革命後のものづくりの機械化のなかで、職人的な手仕事の復権を志向。機械文明の発達により疎外された「労働」を再び活き活きしたものとし、優れた家具など身近な日用品のデザインを通して人とモノの関係を豊かにしようとした、一種の社会運動でもありました。
この動向を語るうえで欠かせないのが、ウィリアム・モリス(1934〜1896)です。「モダンデザインの父」と称されるように、モリスはデザイナーでもありますが、詩人や社会主義思想家の一面も持ち、活動は総合的でした。狭義のアーツ・アンド・クラフツ運動は、モリスの思想に賛同する人々が1880年代から展開した運動の総体を指します。ただ、この潮流の最大の実践者は、やはり、その源流であり、先駆であるモリス自身でした。
モリスの思想の出発点にあるのは、産業革命後の社会や大量生産品の質の劣化に対する強烈な批判意識です。18世紀後半にイギリスで起きた産業革命は、工場制度により生産性を飛躍的に向上させ、都市を拡大し、近代資本主義の発達と労働者階級の誕生を促すなど、社会の土台を大きく変えました。そして1851年、イギリスの工業力を示すものとして世界初の国際博覧会「第一回ロンドン万国博覧会」が開かれます。若き日のモリスはその会場を訪れ、展示された劣悪な工業製品に、途中で見るのを止めるほどの反発を覚えます。
幼い頃から大聖堂に感動する子どもだったモリスは、はじめ聖職者を志望しますが、盟友でのちに人気画家となるエドワード・バーン=ジョーンズらとの交流もあり、建築や芸術の道に進んでいきました。この頃のモリスに大きな影響を与えたものに、評論家ジョン・ラスキンの存在と、彼が擁護したラファエル前派という若い画家の芸術動向があります。
1848年に結成されたラファエル前派は、その名の通り、当時、アカデミーの世界を形骸化させていた盛期ルネサンスの大家ラファエロの模倣を批判し、それ以前、つまり中世や初期ルネサンスの美術や文学に創造の源泉を求めました。その中心的人物であるダンテ・ゲイブリエル・ロセッティは、モリスに絵を教え、またモリスの装飾家としての才能をいち早く見出した人物であり、私生活上ではのちにモリスの妻の愛人ともなりました。
モリスがラファエル前派を知ったのはラスキンを通じてでした。ラスキンは熱烈な中世主義者であり、その著作で芸術家と職人、すなわち創造と労働が明確に区別される前の時代について語りました。労働がそのまま創造の喜びに直結する理想的なビジョンや、良い芸術は良い社会の上に生まれるという考え方は、モリスを大いに刺激します。モリスが手仕事の復権や生活の質の向上を志向する背景には、ラスキンからの強い影響がありました。
1861年、モリスはバーン=ジョーンズやロセッティ、建築家フィリップ・ウェッブら仲間たちと「モリス・マーシャル・フォークナー商会」を設立します。これはステンドグラスから壁面装飾、家具の絵付けなど、住宅から教会までさまざな空間の装飾を全般的に請け負う会社でした。バーン=ジョーンズはステンドグラスの下絵や家具の絵付け、ウェッブは家具のデザインなどと、同社では各々が得意分野を活かした協働が行われましたが、モリスはそれらを束ねる、いまで言うアートディレクターのような役割も果たしました。
多くの職人がひとつの建物を共同制作する姿は、中世のギルドと重なります。それは20世紀の重要な造形学校であるバウハウスが掲げた、建築を中心とするヴィジョンにもつながるものでした(バウハウスについては第一回で取り上げました)。ただ、商会はメンバーの不和などもあり、1875年にモリスの単独経営による「モリス商会」へ変わっています。モリスはその後、歴史を破壊するような修復に反対し、古建築物物保護協会も設立。芸術と社会に関する講演を多く行い、社会主義活動を本格化させていきました。
モリスのデザイナーとしての仕事でとくに有名なのは、壁紙や染色作品のパターン・デザインでしょう。植物を反復的、様式的に描いたそれらは、しかし恐ろしいほどの流麗さや有機性を感じさせます。そのいずれにおいても、モリスは質の向上に徹底的にこだわり、制作プロセスについての実験を重ねました。こうした装飾品に囲まれた生活は、モリスの思想や言葉と合わさることで、より豊かな体験となったのかもしません。
また、晩年の1891年には、自身の印刷工房「ケルムスコット・プレス」を設立。自らデザインした活字と装飾や挿絵が、あたかも中世の大聖堂の如く構築された理想の書物の制作に邁進しました。『ジェフリー・チョーサー作品集』は、その代表的な作例です。
1880年代になると、デザイナーや工芸家が社会のなかで果たす役割を主張する、こうしたモリスの思想や実践を引き継ごうとする若い世代の動きが活発になりました。1882年に設立された「センチュリー・ギルド」などを皮切りに、次々と新しい組織が登場。1884年にはそれらのいくつかが団結し、「アート・ワーカーズ・ギルド」が結成されました。
そのメンバーたちは活動を社会に問う場を求めましたが、旧来の王立美術アカデミー主催の展覧会はいまだ絵画や彫刻中心で、その機会は望めません。そこで団体は自ら定期的な装飾美術のための展覧会組織を立ち上げます。それが1987年設立の「アーツ・アンド・クラフツ展覧会協会」で、翌年に第一回展が開催されました。言うまでもなく、これが「アーツ・アンド・クラフツ運動」の由来です。同展は第一次大戦の時代まで続きました。
ふたたびモリスに戻るならば、その理想と実践は、そもそも大きな矛盾を抱えていたとしばしば指摘されます。というのも、優れた調度品による生活の向上を訴えても、そうした手仕事による高級品を手にできるのは、ごく少数の人々に限られるからです。こうした課題に道筋を見出したのは、アーツ・アンド・クラフツの影響を受けつつも、芸術性とより近代的な産業の融合を目指したドイツ工作連盟や、バウハウスなどの実践でした。
とはいえ、モリスに始まる運動の影響力は幅広く、スコットランドから独自にその精神を解釈したチャールズ・レニー・マッキントッシュのグラスゴー派や、フランスとベルギーを中心に国際的に展開されたデザイン運動であるアール・ヌーヴォー、そのドイツ語圏版であるユーゲントシュティールなど、数多くの動向や潮流の土台を築きました。アメリカの近代建築の巨匠フランク・ロイド・ライトはシカゴのアーツ・アンド・クラフツ協会のメンバーであり、日本で柳宗悦が展開した「民藝運動」にもその影響が伺えます。
そうして考えると、モリスやアーツ・アンド・クラフツ運動の最大の功績は、手仕事の価値を見直したことと同時に、生活を囲む日用品や環境の質によって、私たちの暮らしの質も左右されるという考え方自体を世界に広めたことだと言えるのかもしれません。それはすなわち、「デザイン」の社会的な価値を明確にする動きだったとも言えるでしょう。
杉原 環樹
1984年東京生まれ。武蔵野美術大学大学院美術専攻造形理論・美術史コース修了。出版社勤務を経て、現在は美術系雑誌や書籍を中心に、記事構成・インタビュー・執筆を行う。主な媒体に美術手帖、CINRA.NET、アーツカウンシル東京関連。編集協力として関わった書籍に、卯城竜太(Chim↑Pom)+松田修著『公の時代』(朝日出版社)など。
(この記事は2021/12/30にNewsletterで配信したものです)