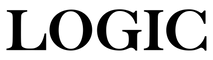LOGIC MAGAZINE Vol.10

LOGIC|SHARE
今、読者の皆さんと一緒に考えたいと感じた
ホットなトピック
現役アートディレクターの視点で見る、佐藤可士和氏が切り開いたもの
現在国立新美術館で開催されている「佐藤可士和展」が盛況だ。コロナの影響で事前予約制ではあるものの、週末となるとすぐに枠が埋まってしまう状態である。佐藤可士和氏は、ユニクロを始め、楽天、ヤンマー、セブンイレブン、今治タオルなど、手がけたブランディングは誰もが目にしているものばかりで、名実ともに日本を代表するクリエイティブ(アート)ディレクターである。かくいう筆者も、スキンケアブランドを運営しながらも現役のアートディレクターでもあり、かつて学生の頃から氏の活躍に憧れを持ち、受けた影響は計り知れない。もちろん尊敬や影響をうけたアートディレクターやデザイナーは時代を越えて他にも多く存在する。そんななか、佐藤可士和氏がおこなったことで一番の偉業だと筆者が考えることがある。それは、プロジェクトの記者発表の場にクライアントの経営トップと肩を並べてクリエイティブディレクターが登場するようになったことである。作ってきたものももちろん偉大だが、そこに注目したい。
元来、デザイナー・クリエイターは黒子であるべきとされていた。各時代を代表する様々な巨匠といえど、表舞台になかなかでることはなかった。しかし、ユニクロでの成功以降、佐藤可士和氏はプロジェクトの度に記者発表のセンターに立ち続け、さらには報道からバラエティまで様々なテレビ番組にも出演し続けている。大きな要因としては2点あり、ひとつは並居る経営トップの側で仕事をし続けたことによりビジネスにおけるデザイン・クリエイティブの重要性を身をもって証明したこと、もうひとつはPRのプロである夫人の佐藤悦子氏の徹底したプロデュース力が佐藤可士和氏自身のブランド化にも成功したことである。氏のビジネス上の戦略であることは否めないが、我々のようなデザイン・クリエイティブの仕事の価値を世の中に啓蒙し続けてくれたのも事実だ。
こうして、佐藤可士和というアイコンが確立されたと同時に、今までクリエイティブディレクターのクの時も知らなかったお茶の間にもその役割や仕事ぶりが少しずつ認知されるようになった。今では、デザインやブランディング関連のプレスリリースに担当クリエイターが紹介されることも珍しくなくなったし、クリエイター自ら自分の仕事をSNSで発表することも一般的になってきた。異論は認めるが、氏の功績によるところが大きいと考えている。話は戻るが、今回の展覧会は、誰もが一度は見たことがあるデザインが多く展示され、その制作過程が事細かに紹介されている。それゆえにデザインの知識や関心があまりない人でも十分楽しめる内容だ。一方、同じ生業をする立場として言えるのは、間違いなく、佐藤可士和氏は歴史を変えた。氏が登場しなければ、今でもデザイナー・クリエイターは黒子であるべきだとなっていたかもしれないし、もっというといちクリエイティブディレクターがこんな大きな展覧会もできなかったはずである。そんな視点も踏まえつつ鑑賞してみるとさらに面白く見れるのではないだろうか。(佐々木智也)
LOGIC | PEOPLE
第一線で活躍するプロフェッショナルの体験や知見から
パフォーマンスアップにつながるヒントを学ぶ。

010
ヘラルボニー
松田崇弥氏
LOGIC MAGAZINE第10回インタビューにご登場いただくのは、「異彩を、放て。」をミッションに掲げる福祉実験ユニット・ヘラルボニーの代表である松田崇弥氏とプレスの中塚美佑氏。同社では、障害のあるアーティストとライセンス契約を結び、アーティストの描くアート作品をさまざまな事業に展開している。福祉を起点に新たな文化の創造を目指す同社の取り組みについて話を伺った。(聞き手:LOGIC MAGAZINE編集部 佐々木、村上)
自閉症のある兄貴が将来幸せになれるか。
そのことを考えて事業に取り組んでいます
―ヘラルボニー創業から2年が経ちました。起業のきっかけは松田さんのお兄さんが自閉症だったことにあると思うのですが、そこから今までの間にいろんな出来事があったと思います。それによってヘラルボニーという会社の輪郭もより浮き彫りになっている気がするのですが、実際のところ、現在はどのようなフェーズになっているのでしょうか。
松田:つい先日もICCサミット FUKUOKA 2021の「ソーシャルグッド・カタパルト」部門で優勝することができたのですが、そのときに審査員が「目指しているビジョンが印象的だった」とおっしゃっていたのがすごく印象的で。スタートアップの多くは、新しい市場を開拓していて、その世界観が広がっていくと世の中が便利になっていくし、それによって社会の在り方も変化していくと思うんです。でも、ヘラルボニーはそういう会社とはちょっと違うのかなって。

左:プレス中塚美佑氏 右:共同代表松田崇弥氏
―具体的に言うと、どのあたりが異なるのでしょうか?
松田:おそらくヘラルボニーがこのまま成長しても社会の在り方は変わらないんですよ。ただ、社会に対する見え方は変わっていくと思います。
―それは松田さんが自身の価値観が変わった経験があるからなのでしょうか?
松田:逆にずっと変わらないんですよね。4つ上の兄が自閉症だったことに加えて、母が毎週末に福祉関係の集まりに参加していたんですよ。だから、いわゆる「障害者」と呼ばれる人たちと過ごすことが多かったので、それが特別なことだと思ったことがなくて。横にいる中塚のお兄さんも自閉症があるんですけれど、それを特別なことだと感じたことはないよね?
中塚:そうですね。この前、松田が「世界一のブランドは、たぶん家族だ」というnoteを書いていたのですが、そこに「自閉症の兄のことを結婚先の家族にどのように説明すればいいのか。受け入れられるのか、不安じゃない?」と質問されたとあって、そういうふうに考える人もいるのかと驚いたんですよね。ちょっとしたショックでもあって。
松田:障害のある兄弟がいる人のことを「きょうだい児」と呼ぶらしくて、心のケアが問題になっているらしいんです。でも、僕自身は大変だった記憶がないから、自閉症のある兄弟がいると結婚できないんじゃないかと思われていることがすごく衝撃で。どっちの考え方がマジョリティなのかはわからないんですけれど。
―松田さんも中塚さんも、自分たちの家族と社会の間に認識のギャップが強くあるからこそ、今の活動につながっているし、二人の家族観みたいなものがもっと多くの人に広がっていけば、社会も変わっていくんじゃないかと考えているわけですよね。
松田:そうだと思います。僕らはヘラルボニーという会社を通じてさまざまな取り組みをしていますが、それらも手段でしかないんですよね。軸にあるのは、兄貴が将来、幸せになれるかどうかで。ヘラルボニーという会社の認知度が広がっていけば、障害もひとつの個性として受け入れらるようになっていくんじゃないかなって考えています。アートライフブランドの「HERALBONY」を立ち上げるときも、地元の友だちもほしくなるものをつくりたいっていう話を会社でしていたんですね。というのも、みんなアートも福祉もそこまで興味ないんですけれど、レクサスとかコム・デ・ギャルソンとかの話はめちゃくちゃするんですよ。それくらいブランド名ってすごいパワーを持っていて。だから、福祉とかアートとかを全面に出すんじゃなくて、「HERALBONY」というブランドをフィルターにして福祉とかアートを紹介したら、興味を持ってくれる人が増えるんじゃないかなって思っています。
いつかは「オタク」のような市民権を
―ゆくゆくは「障害者」という言葉がいらなくなる状態になることが理想なのでしょうか?
松田:どうなんですかね。僕は会社のことを説明するときに「上場までは障害のある人のイメージを変えていくフェーズ、上場以降は障害のある人の生き方を変えていくフェーズ」と言っていて。
中塚:オタクですよね。
―オタク?
松田:社員のみんなには「オタク」みたいなことにならないとダメだと言っていて。10年前くらいは、オタク=犯罪者予備軍みたいな偏見を持っている人ってけっこう多かったと思うんです。でも、今はクールジャパンのひとつとして「オタク」が世界に輸出されているわけじゃないですか。
――カテゴリーのひとつになるということでしょうか。
松田:そうですね。『障害者』が描いているからこの作品は高いんだね」と言われるようになったら面白いんじゃないかなと考えています。

アーティストの作品が絵柄になったネクタイ
各地のアーティストをフックアップしていきたい
―事業を進めていくうえで心がけていることはありますか?
松田:今ってSDGsが盛り上がっていて、ヘラルボニーもその潮流にあえて乗っているところもあるんですけれど、露出が増えれば増えるほど諸刃の剣になると思っていて。だから、やるときは他社から声がかかったときだけと決めていますね。
―自分たちからの発信はしないと。
松田:そうですね。ただ一方で、そういうこととは別に売上はまだまだ伸びるはずだし、社員も爆発的に増えるくらい盛り上がると思っているんですけれど、そこまで至っていないという事実もあって。そこはもっとやれるはずだと思って仕事に取り組んでいます。なかなか難しいんですけどね。
―とはいえ、名古屋に拠点を新しく設置するなど少しずつ前進はしていますよね。
松田:そうですね。今は47都道府県それぞれに拠点を作りたいと考えています。というのも、日本全国の福祉施設でアート活動が盛んになっているんですよ。文化庁も予算をつけはじめていて。でも、現状は発表する場はあるけれど、売る場がない。だから、僕たちが果たす役割があるんじゃないかなって思っています。そういえば、名古屋で森啓輔さんというアーティストのアート作品を展示させていただいてたんですが、そこで「あ、これ森くんじゃん!」って会話されている人がいて。小学校の同級生だったらしいんですけど、そうやって名前が知られていくのってすごくいいなと思ったんです。そうやってそれぞれの地域でアーティストがフックアップされる状況を作っていきたいですね。
______________
松田崇弥さん・中塚美佑さんのパフォーマンスアップのためのルーティーン
「娘の寝かしつけ」
松田:もうすぐ2歳になる娘がいるんですけれど、朝の保育園の送り迎えと夜の寝かしつけは僕がしていて。普段はどうしても仕事のことばかり考えてしまうんですけれど、娘との時間があることで気持ちをリフレッシュできている気がします。あと、娘から必要とされていると思うだけで自己肯定感が高まります(笑)。
「兄のルーティーンを眺める」
中塚:私自身はこれといったルーティーンがないんですけれど、自閉症の兄がルーティーン生活を送っているので、それを眺めているのが日課になっています。必ず朝6時56分に起きて、それからラジオ体操して出社。帰宅時間は16時37分で、家に着いて塗り絵をするところまで見届けています。すごく規則正しい。というか、そうしないと落ち着かないみたいです。
松田崇弥さん・中塚美佑さんのおすすめのワークツール
「小山薫堂さんからもらった名刺入れ」
松田:僕の前職の社長である小山薫堂さんが「チャーリーヴァイス」という鞄のブランドを手がけていて、ひとつ譲り受けて長年使っていたんです。ただ、あまりにも汚くなってしまったので、それを見かねた薫堂さんが「これと交換ね」と言ってマルニのバッグをお下がりでくれることになりました。その後、僕が退職する際に名刺ケースとブックカバーのプレゼントがあったのですが、なんと僕が使っていたチャーリーヴァイスの鞄を裁断して作られたものだったんです。ブックカバーのなかには、薫堂さんが大好きな『アルケミスト』と手書きのメッセージが。本当に粋な方だなと思いました。最近、会社で名刺入れを作ったんですけれど、僕だけは薫堂さんからもらった名刺入れを使っています。
「MUKUのボールペン」
中塚:私がまだ大学生だった頃、ヘラルボニーの前身の「MUKU」というブランドを松田が手がけていて、雨傘のクラウドファンディングをやっていたんですね。すぐに3000円分をポチッとして、リターンとして受け取ったのがこのボールペンです。当時はちょうど卒業論文に取り組んでいて、題材を探していたときに「これしかない!」と興奮したことを覚えています。すぐに勢いのまま松田にメールを打って、後日インタビューもしたのですが、それがきっかけでヘラルボニーで働く機会につながっているので、不思議な縁だなと思います。
LOGIC | CULTURE
教養としてのカルチャーを楽しみながら学ぶ。

「アートのロジック」第2回
『印象派』
知ってるようで知らないアートを読み解く連載「アートのロジック」。第2回は、日本でも人気のモネやルノワールを輩出した印象派について紹介します。
モネやルノワールも当時は酷評された!?
写実主義へのカウンターから生まれた印象派
1874年4月15日、パリにある写真家ナダールの写真館で、ある歴史的な展覧会が開催されました。出品者は、当時まだ駆け出し中のモネ、ルノワール、シスレー、ピサロ、ドガ、セザンヌら、未来の巨匠たち。事物を克明に描く写実主義が美術の主流だった時代、彼らの大胆なタッチは、モネの出品作『印象・日の出』になぞらえて批評家から皮肉的に「印象主義」と称され、この展示はのちに「第一回印象派展」と呼ばれるようになりました。
なぜ、こうした新しい才能による展覧会が開かれたのか。背景には当時の美術界のシステムがあります。19世紀後半、フランスでは保守的な王立美術アカデミーが根強く権威を持っていました。この教育機関では描き方から主題までが規範化され、芸術家の重要な発表の場である国の公募展「サロン」の審査基準も、アカデミズムに基づいていました。
この状況に風穴を開けたのが、印象派の先輩格マネです。マネは60年代に発表した『草上の昼食』などの作品で挑発的なモチーフを取り入れ、物議を醸した存在でした。自身の表現を貫くマネを慕った若い作家は、カフェなどで交流。共同出資会社を立ち上げ、誰でも参加費を払えば出品できるグループ展を企画します。これが「第一回印象派展」です。
印象派の代表的な表現の革新に、「筆触分割・視覚混合」があります。絵具は混ぜるほどに明度が下がり、黒に近づきます。これを回避するため、赤・青・黄の三原色かそれに近い色を塗り重ねることなく細かく配置し、鑑賞者の眼の中で混ぜる方法が生まれました。それにより、印象派の移り行く光の表現や鮮やかな画面が可能になりました。
印象派の多くは、戸外で制作を行いました。ここにはコローら「バルビゾン派」などの先駆者の影響もありますが、主に田園風景を描いた彼らと違い、印象派の画家はむしろ都市生活に目を向けます。当時のパリは現代の姿に向けた都市の大改造期。そこに現れたカフェやオペラ座、新しい街路の光景は彼らの格好の主題になりました。また、写真や日本の浮世絵などの目新しい技術や表現からの影響も、その作品に新規性を与えました。
しかし、色彩理論を追求するモネと、古典主義に立脚し素描を重視したドガの対立にも見られるように、もともと美学的な理念を共有した集まりではない印象派展は、総勢56名もの芸術家が入れ替わり参加したのち、86年の第8回でその幕を閉じます。
一方、その参加者は80年代以降、それぞれの表現を発展させていきます。スーラやシニャックら「新印象派」の画家は、筆触分割をより科学的に展開。セザンヌやゴーギャンたち「ポスト印象派」の画家は、形態の探求やプリミティヴな主題の導入で各々独自の様式を立ち上げていきます。後者に分類されるゴッホも、展示には参加しなかったものの、印象派から大きな影響を受け、激しい色彩による彼の絵画を作っていきました。
また、女性が制度的にも美術界から不平等な扱いを受けていた時代にあって、印象派には少数ながら、メアリー・カサットやベルト・モリゾなどの女性画家も参加していました。近年では、日本国内でも彼女たちの作品を集めた展示が企画されるなど、その存在が注目される機会が増えているように感じます。
このように決して一枚岩ではなかった印象派ですが、この動向がのちの美術に与えた最大のインパクトは、その表現自体と同じほどに、因習的な美術のあり方に芸術家たちが結託して異議申し立てをするという、その態度にあると言えるかもしれません。こうした作家たちの革新性への志向が、20世紀に現れる多様なアートの足場となったからです。
杉原 環樹
1984年東京生まれ。武蔵野美術大学大学院美術専攻造形理論・美術史コース修了。出版社勤務を経て、現在は美術系雑誌や書籍を中心に、記事構成・インタビュー・執筆を行う。主な媒体に美術手帖、CINRA.NET、アーツカウンシル東京関連。編集協力として関わった書籍に、卯城竜太(Chim↑Pom)+松田修著『公の時代』(朝日出版社)など。
(この記事は2021/3/19にNewsletterで配信したものです)