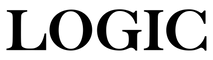LOGIC MAGAZINE Vol.27

LOGIC|SHARE
今、読者の皆さんと一緒に考えたいと感じた
ホットなトピック
LOGIC マイクロミストローション、販売再開のお知らせ
今春から予想を超える注文につき完売していたLOGICマイクロミストローション(ミスト化粧水)の販売を2022年11月8日(火)より再開することをお知らせいたします。欠品状態が続いておりましたが、生産状況が整い、販売を再開することができました。
本商品をご愛用いただいているお客様、本品の購入を検討していた方々にはご迷惑・ご不便をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。
今後ともLOGICおよびマイクロミストローションをご愛願いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
LOGIC代表 佐々木智也
LOGIC | PEOPLE
第一線で活躍するプロフェッショナルの体験や知見から
パフォーマンスアップにつながるヒントを学ぶ。

027
haccoba -Craft Sake Brewery-
佐藤太亮氏
LOGIC MAGAZINE第27回インタビューにご登場いただくのは、福島県南相馬市にあるクラフトサケブルワリー「haccoba」の蔵元を務める佐藤太亮氏です。IT企業に勤めていた佐藤さんがhaccobaを立ち上げたのは2021年2月のこと。新興産業から伝統産業へ。ある意味、正反対の仕事に就くことになった佐藤さん。そこにはどのような想いがあったのでしょうか。(聞き手:LOGIC MAGAZINE編集部 佐々木、村上)
素人だからこそできる
酒造りの開拓を
ー佐藤さんはどのようなきっかけで酒造りに取り組みたいと考えたのでしょうか?
佐藤:東京で大学生活を送っていたとき、個人経営の小さな和食居酒屋でアルバイトをしていたことがあって。そのときに日本酒の美味しさと奥深さを知りました。
ーこんなに多様な在り方があるんだなと。
佐藤:それとは別に、石川県の能登半島にある会社で半年ほどインターンでまちづくりに寄与したのですが、地域文化の担い手として貢献する日本酒や味噌、醤油などの醸造家と接する機会があって、彼らの生き様に憧れを抱きました。ただ、伝統産業に参入することの難しさは学生ながらに理解していたので、やりたいなと思いつつ諦めていたというか、そのときは踏み出す勇気がなくて行動に移せなかったんです。それで普通に就職しました。
ー何が転機に?
佐藤:2社目がIT系のスタートアップだったこともあり、その界隈の方々と接する機会が増えたんです。なかには日本酒の事業に取り組んでいる方もいて、お手伝いさせてもらうこともありました。それで次第に自分でもできる方法があるんじゃないかと考えるようになって、実際に取り組むようになったっていう。
ースタートアップに転職したことで、結果として自分のやりたいことを手繰り寄せたんですね。今と昔でガラリと生活が変化していると思うのですが、どちらのほうが楽しいですか?
佐藤:くらべるのは難しいですね、どちらも好きなので。前職ではプラットフォームサービスに携わっていたのですが、世界を良くしていく仕組みをつくっている感覚があってすごくワクワクしました。そういう粒度で話をすると、今はコンテンツをつくっている感覚に近いのかなと思っていて。僕たちの酒蔵では、クリエイターやブランドと一緒にお酒を通じた体験をつくることに取り組んでいるんですね。そうやってお酒造りをしたことがない人たちを巻き込んでコンテンツ化していくのが面白いと思っていて。
ーそれはお酒造りをするなかで考えるようになったことなのでしょうか? それとも、佐藤さんの気質として?
佐藤:性に合っているんでしょうね。もちろん昔ながらの製法にこだわってつくるのもいいと思うんですよ。伝統産業ですから。ただ、僕らはあくまでも新興企業なので、既存の人たちが挑戦できないことに取り組むほうが意義があるんじゃないかなと。ある意味、素人だからやれることがあるというか。
ー確かに、経験を積み重ねるからこそ初心を忘れていくし、怖いもの知らずだったのがいつの間にか怖いものだらけになることもある気がします。
佐藤:そうですね。とはいえ、僕たちも経験値がどんどん積み重なっているので、素人の視点を入れ続けるためには、他ジャンルの方々と酒造りをするほうが良いと思っています。一方で、多くの先達が継承してきた伝統や文化に対するリスペクトを忘れないことも重要で。そこは絶対に忘れないように意識しています。僕らは、日本酒や発酵文化を繋いでいきたいからこそのチャレンジをしてるだけであって、対立構造を生み出したいわけではないので。
酒造りには営みの美しさがある
ー佐藤さんが話されていることは人付き合いにおいて大切なことですよね。酒造り自体の魅力についてはどのように考えていますか?
佐藤:営みの美しさがあるなと。実は日本酒って、人間がつくっているようで、そうじゃないんですよね。
ーといいますと?
佐藤:日本酒って微生物の発酵によってつくられるものなんですね。僕らでコントロールしきれない領域がすごく多い。しかも、同じ工程でつくったとしても同じ味のものが完成するともかぎらない。エンジニアリングみたいに思い描いたものをつくりきれないんですよ。それに飲んでしまったら終わりじゃないですか。絵画や音楽みたいにずっと残し続けられるものでもない。そういう意味では、再現性が低く、刹那的なものづくりなんです。だからこそ、美しいなって。
ーすごく神秘的ですね。
佐藤:そうなんです。だからこそ、神と交信するためのツールでもあるわけで。ただ一方で、すごく俗的に使われることもありますよね。飲み会で簡単に酔うために日本酒が大量に消費されることがあるじゃないですか。そういう両面性がある存在だなと思っています。
日本酒をもっと日常に近づけていきたい
ー佐藤さんが酒蔵をつくって1年半ほど経ちました。理想と現実のギャップはありますか?
佐藤:思っていた以上にさまざまなジャンルの方々とお酒造りができたなと思います。その経験があるからこそ、今も楽しく働けているのかなと。一方で、想像よりも大変な仕事だなと思いました。前職とくらべたときに、こんなに労力に見合わない仕事があるのかと思うこともありますし(笑)。100年とか200年とかのスパンで酒蔵を続けていらっしゃる方から話を聞かせていただく機会もあったので、わかっていたつもりなんですけどね。
ーそれでも佐藤さんが酒造りを続けられているのはなぜなのでしょうか?
佐藤:自分たちがやりたいことって、日本酒における新しい文化をつくりたいっていうよりは、発酵文化の源流みたいな酒造りの自由で多様な文化を取り戻したい気持ちが強いんですね。そういった活動って一朝一夕ではどうにもならないというか、時間の経過のなかで積み重ねていくものが想像以上に大事だと感じていて。スタートアップ企業のように数年でスケールさせるような働き方とは根本から違うと言いますか。次の世代やさらに次の世代にどう継承していくか、みたいなことを今のうちから意識しておくべきなんだと。ほら、老舗の和菓子屋さんってただならぬ空気を感じるじゃないですか。
ー佐藤さん自身は積み重ねている感覚はありますか?
佐藤:同時代の人たちに向けてという意味だと、少しずつ積み重ねてこられたのかなという手応えはあります。ただ、次の世代に継承することを考えると、酒蔵の1代目としてどう振る舞うべきかを考えなければいけないと思うようになっていて。持続可能な組織をつくるとか、将来世代のことも考えた資源の使い方をするとか。できることはたくさんあると感じています。
次の世代、その次の世代のことも考えた酒造り
ー理想の1代目像に近づくことが、佐藤さんがこれから取り組むべきことになるのでしょうか?
佐藤:そうだと思います。最近すごく考えるのは、老舗と呼ばれるような酒蔵の1代目って、その時代においては同業者から「やりすぎでしょ」って反対されるような、ある意味における狂気性みたいなものを持ちながら酒造りに取り組んでいたんだろうなと。だからこそイノベーションを起こすことができたんだろうし、今でも残り続けているんだろうなって。
ー佐藤さんもそうありたい、と。
佐藤:そうですね。そのうえで、僕は日本酒をもっと日常と近づけていきたいんです。これは個人的に考えていることなのですが、伝統文化と呼ばれるものって大衆性が薄れているような気がするんですよ。生活者にとっての日常から離れていくというか。日本酒もどんどんそうなりつつある気がするんです。たとえば、冷蔵庫のなかを見たときに、日本酒より缶ビールが入っているケースのほうが多いはず。
ー日本酒がケのものではなく、ハレのものになっているということですね。
佐藤:だからこそ、日常における日本酒のあり方をいかに構築していくかを考えることが、さらに重要になる気がしています。そのためは、その時代その時代ごとに日本酒と生活者の関係を結び直すことが大事なのかなと。それにこれから取り組みたいですね。
______________
佐藤太亮さんのパフォーマンスアップのためのルーティーン
「起きる時間を固定する」
生活のリズムを大事にしたいと考えているので、平日・休日関係なく、7時頃に起きるようにしています。寝る時間はどうにもコントロールできないときもあるのでバラつくこともあるんですけど。。
「酒造りのシーズンが終わったら納豆を食べる」
米麹をつくる際、願掛けの意味も含めて乳酸菌や納豆菌のような酒造りに影響のある菌類に触れないようにしているんですね。だから、酒造りのシーズンが明けたら納豆を死ぬほど食べています(笑)。実際のところ、市販で売られている納豆で菌の強いものは売られていないのでそこまで影響はないのですが、「納豆を食べられない」っていうプロレスをやるのが楽しいんですよ。
「チョコレート補給」
僕は甘いものが大好きで、仕事中の糖分補給が欠かせません。なかでも「ダンデライオン・チョコレート」と「Minimal」がお気に入りです。サブスクを申し込んでいて、定期的に届くのを楽しみにしています。
「仕事をしながらポッドキャストを聴く」
「TAKRAM RADIO」「COTEN RADIO」からお笑い芸人の岡田康太の「ポッドキャスト」に至るまで幅広く聴いています。
佐藤太亮さんのおすすめのワークツール
「ニット帽」
僕、昔は髪がけっこう長かったんですけど、酒をつくるようになってから坊主にしたんですよ。というのも、酒蔵で作業するときにタオルや手拭いを頭に巻くのですが、跡がつくんですね。その状態で外に出たくなくて。それでニット帽を被るようになって、今ではすっかりユニフォームみたいになっています。妻がパタゴニアのキャップを買ってくることが多いので、パタゴニア率が高いですね。
「アレクサ」
SwitchBotと組み合わせて酒蔵の温湿管理をしたり、作業の時間を計測したり、蔵のなかで音楽を聴いたりしています。
「うがい薬と葛根湯」
仕事がらいろんな人に会うので、予防も兼ねてうがいと葛根湯で体調管理を徹底しています。
LOGIC | CULTURE
教養としてのカルチャーを楽しみながら学ぶ。

illustration:うえむらのぶこ
「ビジネス映画学」第5回
『マイレージ、マイライフ(Up in the Air)』
ビジネスにおいてピンチに直面したとき、どのように振る舞えばいいでしょうか。『マイレージ、マイライフ』は、こうした問いに対してあらゆる視点での気づきを与えてくれます。
主人公のライアンは、人事コンサルティング企業に勤めています。具体的な職務は、企業から委託されて社員へのリストラ勧告を請け負うこと。もちろん、リストラを告げられた社員たちには口汚く罵られます。加えて、米国中にある企業を尋ね回らねばならないので、自宅にはほとんど帰れません。一見すると誰もやりたくない仕事のように思えますし、ブラックと言われるかもしれない働き方です。まかり間違ってこんな仕事をすることになったら、それこそピンチでしかないでしょう。
しかし、ライアンが嫌々仕事をしているのかと言えば、そうではありません。むしろ彼なりのやりがいを見出しており、天職と思っているフシすらあります。しかも、そうした出張を通して、アメリカン航空史上7人目にして最年少での1000万マイル達成者になるというプライベートでの夢も叶えようとしているわけですから、いわゆる“やりがい搾取”に邁進しているわけでもありません。家族をはじめとする深い人間関係に関心がない彼にとって、遊牧民のようなこの仕事はすこぶる性に合っているということなのでしょう。
そうした人生観は、彼が講演会で語る内容にも示唆されています。彼は講演台の横にバックパックを置き、こう言い放つのです。「このバックパックに荷物を詰めるのと、人生は同じだ。我々はその重荷で動けなくなっている。火事になったら? 写真? 心に刻めない記憶など捨ててしまえ。すべて燃えて身軽になった自分を想像しろ」と。要するに、「身軽に生きる」が彼のモットーというわけです。ピンチと思われる仕事であっても、自分が大切にしていることさえはっきりしていれば、“搾取”とはまた違うやりがいを見出しうるということが、ここでは描かれているのです。
そして、「身軽に生きる」というモットーの持ち主だからこそ、ライアンはビジネスマンがリストラされるというピンチも重くは考えておらず、クールに勧告できるのでしょう。仕事を失うということは、視点を変えれば「身軽に」なることへの入り口かもしれないからです。実際、ライアンは、リストラを告げられ動揺を隠しきれないある男性に、彼がフランス料理の学校を卒業したという経歴を着目してこう語りかけます。「生涯ひとつの会社に勤め続ける人を見てきた。時間に縛られ、幸福を知らない。君は今がチャンスだ。生まれ変われる」と。つまり、せっかく身軽になったんだから、かつての夢であった料理人になる夢を追いかけてはどうかと提案するわけです。詭弁と言えばそれまでですが、男性もまんざらではありません。ライアンに言わせれば、リストラというピンチは自分を見つめ直すチャンスでもあるのです。
そんなライアンにも職務上のピンチが訪れます。会社が経費削減と効率化を理由に、対面からオンラインビデオチャットでの勧告に切り替えるというのです。1000万マイル達成者になるという夢を追いかける彼は、これに猛反対。何とか決定を覆すべく、オンライン切り替えを提案した新人と一緒に出張に行くことにします。興味深いのは、ライアンがその旅路での出会いや経験を通して、この仕事が対面であることの重要さに気づく点にほかなりません。
先述のとおり、彼は深い人間関係に関心がないと自覚していました。しかし、むしろ仕事で得られる束の間の人間関係でもって、その埋め合わせをしていたのではないか。対面であることにこそ、やりがいを感じていたのではないか。マイルを貯めるのは、それに付随する些事でしかなかったのではないか。そんなことを思うようになります。結果、ライアンだけに限っては、これからも対面での勧告を許されるのですが、この出張は彼を飛躍的に成長させることになるのです。
ピンチはチャンスなんていう使い古された言い回しがありますが、『マイレージ、マイライフ』を観ると、それはビジネスにとっても真実のように思えてきます。
鍵和田 啓介
1988年生まれ、ライター。映画批評家であり、「爆音映画祭」のディレクターである樋口泰人氏に誘われ、大学時代よりライター活動を開始。現在は、『POPEYE』『BRUTUS』などの雑誌を中心に、さまざまな記事を執筆している。
(この記事は2022/11/07にNewsletterで配信したものです)