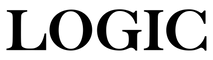LOGIC MAGAZINE Vol.29

LOGIC|SHARE
今、読者の皆さんと一緒に考えたいと感じた
ホットなトピック

『LOGIC』が新進気鋭のクリエイターとコラボを通じて応援するプロジェクト『LOGIC CO-CREATION LAB』を始動。
様々な分野の新進気鋭のクリエイターとコラボレーションを通じて応援するプロジェクト『LOGIC CO-CREATION LAB』を始動することになりました。
LOGICは発売以来、「LOGIC MAGAZINE」などのメディアやコンテンツを通じ、ビジネスの教養としてのアートを発信してまいりました。特に私たちの顧客層である20代〜40代のビジネスパーソンにとって、アートは見聞を広めたり、インスピレーションのヒントとしてとても有意義な領域だと考えております。
『LOGIC CO-CREATION LAB』は、LOGICのプロダクトやコンテンツを用いたコラボレーションを通じ、クリエイターの表現や活動の幅を拡げたり、応援することを目的としたプロジェクトです。今後も様々なクリエイターとの企画を実施していく予定ですので、是非ご期待ください!ユーザーの皆様が新たな才能と出会うきっかけになれば幸いです。
まずはプロジェクト第一弾として、イラストレーターとして活躍するオガワナツミさんに、オーガニックコットン製ギフトパッケージのイラストを描き下ろしていただきました。3月8日より『LOGIC』公式オンラインストアにて数量限定で先行販売いたします。ギフトにもぴったりですので、ぜひチェックしてみてください。
オガワナツミさんとのコラボギフトはこちら
https://logic.tokyo/products/logic-ogawa
オガワナツミさん プロフィール

イラストレーター。1993年、新潟県生まれ。様々なアーティストやブランドとのコラボグッズのデザインやテレビ番組などのロゴやキャラクターのデザインを手がける。
Instagram:https://www.instagram.com/ogwillust/
LOGIC | PEOPLE
第一線で活躍するプロフェッショナルの体験や知見から
パフォーマンスアップにつながるヒントを学ぶ。

029
株式会社小杉湯
平松佑介氏
LOGIC MAGAZINE第29回インタビューにご登場いただくのは、株式会社小杉湯の平松佑介氏です。昭和8年創業の老舗銭湯を引き継ぎ、現在7年目。斜陽産業と呼ばれる一方で、熱心に通う人も多い「銭湯」というビジネスに対する想いについて尋ねます。(聞き手:LOGIC MAGAZINE編集部 佐々木、村上)
次の世代に最高のかたちでタスキを。銭湯を未来に継承していくための決意
ーこのインタビューでは「夢中」をテーマに話を伺っています。この「夢中」という言葉から思い浮かぶことはありますか?
平松:真っ先に思い浮かぶのは「危機感」ですね。
ー危機感?
平松:僕は今から7年前の36歳のときに先代から小杉湯の経営権を継承し、今に至るまで試行錯誤を繰り返してきました。ただ、やればやるほど銭湯というビジネスの難しさを痛感するようになっていて。もちろん夢中で事業に取り組んでいますし、小杉湯のような場所が社会的にも時代的にも必要とされているという実感もあるんです。「小杉湯に救われた」「小杉湯があるから高円寺に引っ越してきた」という人がかなりの数いるので。ただ、その裏には常に危機感があるんですよね。
ーそんなに難しいものですか?
平松:小杉湯は古い建物ということもあり、国の有形文化財に登録されているのですが、修繕のために400〜500万円は毎年かかるんですよ。しかも、小杉湯は歴史を重ねてきた建物なので、毎年のメンテナンスに加えて20〜25年の間隔で大規模な修繕も行わなければいけません。
ーとはいえ、定期的なメンテナンスは必要ですよね?
平松:そうですね。小杉湯をこの先10年、20年、30年と続けていくことを考えると、どこかのタイミングで絶対にやらなければいけません。ただ、実行するとなれば最低でも半年間は休業しなければならないので、今度は雇用を維持することが難しくなります。
ー解決策を導き出すまではたどり着いていない?
平松:結論から言うと、小杉湯の入浴料だけで事業を継続していくのは難しいと考えています。だからこそ、銭湯以外の場所で稼げるポイントをつくらないといけないし、つくろうとしているのが現状です。
共同体のつながりを事業に
ー具体的に取り組んでいることはあるのでしょうか?
平松:共同体のつながりを事業にしていこうと取り組んでいます。たとえば、小杉湯の隣にある「小杉湯となり」というシェアスペース。ここは初代が建てた風呂なしアパートをリノベーションするかたちで2020年3月に生まれたのですが、運営は「銭湯暮らし」という小杉湯のファンのつながりから生まれた会社が行っていて。僕や小杉湯のメンバーは事業に関わっていないんですよ。
ーファンのつながりから生まれた会社というのはユニークですね。
平松:すごく面白いのが、「小杉湯となり」という場所をつくってから人が集まったのではなく、それ以前に空き家に集っていた人たちが繋がって会社になっているということなんですね。しかも運営メンバーのほとんどが高円寺に住んでいて、自分たちの暮らしに小杉湯や小杉湯となりが必要だからという動機で運営に関わっています。加えて、小杉湯となりを利用している会員が50〜60人ほど、小杉湯や小杉湯となりのメンバーも含めると200人規模の有機的なつながりができるわけです。そうすると何が起こるかというと、あっちこっちでイベントが生まれるんですよ。
ーそして、さらにつながりができるわけですね。
平松:初代が残してくれたアパートに人が集まり、小杉湯を中心とした半径500m以内に共同体ができあがる。彼らにとって、小杉湯はお風呂で、小杉湯となりはリビングや台所、書斎なんです。
ー家の範囲が拡張されていく、と。面白いですね。
平松:高円寺に引っ越してきてくださる方のなかには、小杉湯の存在を理由にしている場合が一定数あるんですね。そういう方々に対して「銭湯付き物件」の提案もしています。
ー銭湯付き物件?
平松:高円寺にある空き家を活用するかたちでリノベーションをしているのですが、都内の銭湯で使える1カ月分の入浴券を付けているんです。3部屋の募集に対して50名の応募があり、こういう暮らしを求めている人は一定数いるんだと実感しました。500m圏内の中心に小杉湯があれば、入浴料だけではなく、寄付みたいなものも成立するかもしれないし、行政からも今までとは違う助成金の受け取り方があるかもしれないと考えています。あとは企業とのコラボレーション。光栄にも、小杉湯のようなローカルでニッチなコミュニティに興味を持ってくださるケースがあるので、うまく掛け算を起こしていきたいんですよね。
事業は3代目が要
ー平松さんは今、銭湯を起点にしたコミュニティをどんどん増やしていきたいと考えているわけですよね。
平松:増やしていきたいし、増やしていかないといけないと思っています。実は今、このモデルを高円寺だけでなく、別の地域でも実践していきたいと考えていて。新たな銭湯をつくるか、後継ぎ問題を抱える銭湯を引き継ぐか、まだわからないのですが。というのも、僕自身がゴールを掲げてこの場所にたどり着いたのではなく、危機感からくる「このままじゃ無理だよね、でも可能性はいっぱいあるよね」からとにかく頑張ってきて、その結果として今があるだけなので。
ーたとえば、事業譲渡のようなことも選択肢のひとつにあったわけじゃないですか。そうすることで、肩の荷が降りる場合もあると思うんです。その選択をしないのは、平松さんとしては何が大きな拠りどころになっているのでしょうか?
平松:家業だからですね。これが僕のはじめた事業だったら、子供に引き継いでほしいとは思わなかったと思います。平松家に生まれ、初代、2代目と継承されているからこそ、次の世代にタスキを繋いでいきたい気持ちが強いんですよね。
ーどのような状況でタスキを渡したいという理想はあるのでしょうか?
平松:「事業は3代目が要」みたいに言われることが多々あるじゃないですか。確かにそうだなと思う部分が僕にもあって。2代目までは初代のやってきたことを見よう見まねで続けられると思うんです。ただ、3代目となると初代が働いている姿を見る機会がほとんどないんです。そのうえ時代が大きく変わっているので、初代と同じやり方をしてもうまくいかないことが多くなります。だから4代目、5代目とタスキを継承していくためには、3代目の役割がすごく重要になるんですよ。
ー箱根駅伝で言うところの5区みたいな感じなんですかね。この区間で活躍して「山の神」になれるかどうか、みたいな。
平松:いずれにせよ、この10年以内には大規模な修繕をしなければいけないんですね。僕は今年で43歳なので、なんとか50歳までにその課題に取り組んで、50年後、100年後を見据えた銭湯の在り方を示していければいいなと考えています。それが僕の使命なのかなって。
______________
平松佑介さんのパフォーマンスアップのためのルーティーン
「空き時間に入浴する」
仕事をしていると、ちょっとした空き時間が生まれるじゃないですか。15〜20分くらいの空き時間があれば、入浴するようにしています。そうすると、思考が整理されて良いアウトプットが出せるんですよね。
平松佑介さんのおすすめのワークツール
「パタゴニアの服」
老舗銭湯の経営という長い歴史を紡いできた仕事をしていることもあり、パタゴニアのサスティナビリティを追求する企業姿勢がすごく好きで。環境への意識に共感するし、アウトドアも好きだし、着心地も良いし、よく着ています。
LOGIC | CULTURE
教養としてのカルチャーを楽しみながら学ぶ。

「ビジネス映画学」第6回
『アビエイター』
ビジネスマンにはロジカルな思考が大事だとよく言われます。実際、採用募集の「求める人材」欄には、「論理的な思考ができる人」という記述がしばしば見られます。たしかに、複数名でプロジェクトを進める場合、密なコミュニケーションは必要不可欠であり、そこでは論理的な思考によって紡ぎ出された、誰にでもわかる説明が求められるでしょう。しかし、もし上に立つ者なら、あるいは上に立つ者を目指すなら、論理とは真逆の感覚的な判断が効果を発揮する場合もあるかもしれません。そんな気付きが得られるのが、『アビエイター』です。
同作は、1905年に生まれた起業家ハワード・ヒューズについての伝記映画です。石油王の父と名家出身の母を相次いで亡くし、受け継いだ莫大な遺産をもとに、さまざまな事業(趣味の延長とも言えますが……)に挑むヒューズを、レオナルド・ディカプリオが演じています。
まず、スポットが当てられるのは、ヒューズが監督を務めた飛行機映画『地獄の天使』の撮影風景です。とにかく彼のこだわりがとんでもない。完成に数年を要し、制作費も史上初の100万ドルを越えてしまうのですから。しかも、ヒューズは映画会社の社員ではないので、これは私財を投じた自主映画なわけですが、1930年に公開されるとまたたく間に大ヒットを飛ばし、今では飛行機映画の傑作としてその名を歴史に刻んでいます。さすがと言うしかありません。
続いて彼が乗り出したのが、飛行機事業です。自ら製造した飛行機で、アメリカ大陸横断のスピード記録を二度も樹立した彼は(タイトルの『アビエイター』とは飛行機乗りを意味します)、飛行機への愛が長じて大手航空会社であるTWA社を買収し、路線拡大に乗り出しそうと目論みます。映画のクライマックスを飾るのは、そんな彼が商売敵のパンナム社との政治家を巻き込んだ駆け引きに勝利する姿です。
映画を観ているとわかるのは、ヒューズが度を越した完璧主義者であることにほかなりません。そして、それは“手”にまつわる描写を通して強調されます。そもそも本作の最初のシーンは、幼児期のヒューズの体を、潔癖症だった母が入念に手で洗う姿なのですが、これが引き金になったとでも言うかのように、大人になったヒューズは“手の男”として、もっと言えばビジネス的な決断をする際は、“手の感覚を信じる男”として描かれているのです。
たとえば、長引く『地獄の天使』の資金を捻出するため、会社と全資産を抵当に入れると決断するとき、彼は自分の手をじっと見つめます。あるいは、新しい飛行機を製造する際も、試作品の表面を舐めるように手で撫で、「リベットの頭を沈めろ! つなぎ目もなめらかにしろ!」と無茶なダメ出しをしたり、ハンドル一つ決めるのにも8000種類を実際に握って選ぶのです(手に関して言えば、彼は母親と同じく常軌を逸した潔癖症であり、そのことに悩む姿も本作では時間を割かれているのですが、これは手の感覚への信頼がネガティブに作用した例と言えるかもしれません)。
これらはすべて個人的な手の感覚を頼りにした独断であり、ロジカルでもないから常人には理解できません。だから、彼の下につく者たちは振り回される一方なのですが、ヒューズがそのほとんどの事業で成功を収めてきたことを鑑みるなら、その感覚的判断が功を奏したと言えるでしょう。もちろん、ただ暴君として振る舞えばいいわけではありません。その感覚はそれぞれの事業に対する常軌を逸した愛情に裏打ちされており、そのような感覚を磨くのも大事なことがわかります。
興味深いことに、アマゾンの創業者ジェフ・ベゾスもまた、ビジネス的な視点において本作の手の描写(前述の「リベットの頭を沈めろ!」の描写)に注目しているようです。ベゾスの右腕として知られるビル・カーの著書『アマゾンの最強の働き方』で、こんなエピソードが紹介されています。
アマゾンのとあるサービスが失敗に終わった後、ベゾスはその責任者スティーブ・ケッセルに『アビエイター』の例のシーンを解説し、「ハワード・ヒューズのようになるのがきみの仕事だ」と告げたそうです。以後、スティーブは、アマゾンのすべてのプロダクトを“指でなぞる”ようになり、質を低下させそうな点がないか確認し、チームに最高の水準を維持するよう言い続けたそうです。カーは、スティーブがこの話を自分にした理由を以下のように分析しています。
「一つはある種の警告だ。彼のチームの主要なメンバーである私とそのチームに、プロダクトが基準に見合わなければ最初からやり直しを命じると知らせたかったのだろう。もう一つは、私にも高い水準を追求する責任があると暗に伝えようとしたのだ。私自身もハワード・ヒューズに近づく必要があった」
要するに、一連のエピソードを「高い水準を維持せよ」というメッセージとしてカーは(そしてスティーブも)受け取っているわけですが、ビジネスの大前提であるそんなエールを伝えるために、ベゾスは『アビエイター』に触れたのでしょうか。むしろ、その「高い水準」へと導くためには、メンバーに理解されなくとも、事業への常軌を逸した愛によって感覚を磨き、それでもって重要な決断をすべきであると、ベゾスは教えたかったんではないしょうか。「ハワード・ヒューズのようになるのがきみの仕事だ」とは、そういう意味だと個人的に思うのです。
鍵和田 啓介
1988年生まれ、ライター。映画批評家であり、「爆音映画祭」のディレクターである樋口泰人氏に誘われ、大学時代よりライター活動を開始。現在は、『POPEYE』『BRUTUS』などの雑誌を中心に、さまざまな記事を執筆している。
(この記事は2023/03/14にNewsletterで配信したものです)