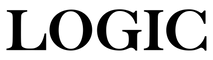LOGIC MAGAZINE Vol.36

LOGIC | PEOPLE
第一線で活躍するプロフェッショナルの体験や知見から
パフォーマンスアップにつながるヒントを学ぶ。

036
mount inc.
イム・ジョンホ氏
LOGIC MAGAZINE第36回インタビューにご登場いただくのは、mount inc.(以下mount)のイム・ジョンホ氏です。Webサイトの企画・制作を軸にデザイン領域で活動し、これまで数々のアワードを国内外で受賞してきたイム氏ですが、ここ数年は仕事に対する考え方に変化があったとか。何が起きたのかを聞きます。(聞き手:LOGIC MAGAZINE編集部 佐々木、村上)
mountの文化を未来に繋ぐために
40代からはじめた組織づくり
―このインタビューでは「夢中」をテーマに働く原動力を探っているのですが、mountの仕事といえば、圧倒的なクオリティが特徴のひとつにあげられます。いつも難易度の高いことに挑戦している印象があるのですが、何がイムさんを突き動かしているのでしょうか。
イム:それでいうと、夢中というより「必死」という言葉のほうが合っている気がします。そもそも私は、デザインのバックグラウンドがないまま独学ではじめたので、仕事をしはじめたときからコンプレックスが常にあり、20代、30代はそれを打ち消すように必死でものづくりに取り組んでいました。
―どういった部分でコンプレックスを感じていたんですか?
イム:常にあるのは自分に対する至らなさです。知識のなさ、技量のなさなどに対する至らなさをずっと感じていました。私のキャリアのスタートになったビジネスアーキテクツという会社には、すごい先輩ばかり在籍していたんですね。彼らはデザインのバックグラウンドをはじめとして文学、映像、音楽などをはじめとするカルチャーに対する造詣も深かった。デザイン領域以外のパートでもとにかく「すごい」先輩たちがいっぱいいました。私が勝てる要素が何ひとつもないわけです。在籍中、彼らに追いつくためにいろんなことを努力してもコンプレックスは消えず、勉強することを言い訳に会社をやめたんです。でも、結局何もやらなかった。向いてないことに気づいて、どのようにものづくりに向き合おうか考えた結果、自分が得意な仕切りと高い精度のデザインに集中し、それ以外はできる人とやろうと決めたんです。
―いつ頃の話ですか?
イム:28歳頃ですね。フリーランスになって2年目に入った頃です。仕事のスタンスを定めたあとは写真、映像、言葉、インタラクションなどに対してプロジェクトごとに挑戦ポイントを定め、アートディレクターと名乗れるようになるために挑戦し続けました。その後、31歳になる年に梅津(岳城)と一緒にmountを立ち上げることになります。当時は自分がつくったものに対して自分が感動できるものをつくりたい気持ちが強かったです。そんなものは滅多につくれないので、幻を追いかけるような気持ちでした。
―極端なことを言えば、自分が感動できれば他人の評価を気にせずにいられたということでもありますか?
イム:それはちょっと違っていて。自分さえよければいいとは思わないんです。主義じゃないというか。デザイナーという職業は、クライアントからお金をいただいてものをつくるという点に関して意識的でなければいけないと思うんですね。私情が優先されるべきではない。だからこそ、クライアントが抱える課題や悩みをきちんと解決できるものをつくりたいし、それを叶えたうえで自分のこだわりやチャレンジを何かひとつ差し込みたいと考えてました。そのうえでの感動ですね。
―自らの意思でものづくりのハードルを上げていたわけですね。
イム:振り返ってみると、私が成し遂げたいのは「よいものをつくりたい」という一点なんです。mountは「よいものであり、明快かつ、心が動くものをつくる」を目指していますが、その実現のために何をしたら最善なのかという軸でずっと考え実践してきました。ときに自分の能力以上の仕事が舞い込んできて、「なんでこんな仕事を受けてしまったんだ」と不安に押しつぶされそうになることがありながらも、そのプレッシャーを必死にもがくことで原動力に変えていたんです。
100通りの選択肢より、ひとつの答え
―クオリティの高いものをつくるにあたって、クライアントの理解は欠かせないですよね。場合によっては、そこまでのものを求められていないということもあると思うのですが、どのように合意形成しているのでしょうか?
イム:前提にあるのは、「なぜ私たちに仕事を依頼するのか」ということだと思うんですね。極端なことを言えば、ただWebサイトを制作するだけならAIを使えばいい。好きなだけアウトプットをつくれますよ。でも、選択肢が100あっても実は意味がないんです。そのなかで何がベストな選択なのかわからないから。だから、私たちは「この人たちは私たち以上に私たちのことを理解している」と感じてもらえるくらいにたくさんヒアリングやコミュニケーションをして必要なことをすべて言語化し、ときにロジカルに、ときにはエモーショナルに説明します。ちゃんと寄り添ったものづくりのプロセスをしてるからこそ、“一案のみ”の提案が通り続けたんだと思います。
―何が大きく作用して案が通っていると思いますか?
イム:共感力ですね。かつて上田義彦さんという写真家のWebサイトを制作したことがあるのですが、あるとき「どういう気持ちで、どういう時にシャッターを切るんですか?」と聞いたところ、「私、すぐ好きになっちゃうんだよね」とおっしゃったんです。つまり、愛しいと思う瞬間にシャッターを切っているんだと。私たちとクライアントの関係も似ていて、共感できるからこそ、「正しくて、適切なもの」を提案できます。だから、まずは自分たちがクライアントのことを共感できるように前提づくりにたくさん時間をかけています。
―クライアントの合意を得るためには、予算やスケジュール、人員の問題などクリアしないといけない条件がさまざまにあります。それはどう解決しているんですか?
イム:仕事を依頼されたタイミングで、私たちがどのようにプロジェクトを進めて、何を目指すのかをきちんと説明するようにしています。その時点でクライアントはある程度どのような仕事になっていくか想像ができるようになります。そのうえで先ほど申し上げたように丁寧なヒアリングから要件定義や方向性の提案を行なって納得いただく流れをつくります。その過程でクライアントの事情も加味しますので、そこまで大きなずれは起きません。あとは期待感を醸成することですね。「世界一のWebsサイトをつくります」とよく言うのですが、クライアントのコミットメントが上がり、自分たちのハードルも上がる。これを言っちゃったら、もうお互いにやるしかないんですよね(笑)。
プロセスの99%は辛い。それでも、1%の喜びのために
―そうした経験を積むなかで自分のレベルが高まっていくし、それによってクライアントに提供できる価値もどんどん高まっていくわけですよね。今もそれをより高めていくイメージですか?
イム:いいえ。30代後半くらいから自分ができることがよりわかってきて少しずつ考え方が変化しました。いま私が力を注いでいるのはmountの文化を残していくことです。
―なぜそのように考えるようになったんですか?
イム:端的に言うと、老いですね。月日には逆らえないと言いますか。40代に入ってからは無理もできなくなってきました。だって、老眼鏡をかけないと文字が読めないんですから。自分の身体が衰えていくことも認めなければいけません。気力も体力も低下していくなかで、これまでのように高いクオリティのものがつくれないじゃないかという、今までとは異なる不安は増すばかりです。かといって、仕事をしていない自分は想像できない。
―仕事がアイデンティティを保つ要素になっていると。
イム:はい。こんなことを言っていると「イムさんは仕事が好きだ」と思われるのですが、本当は好きじゃないんです。仕事の99%は辛いと思っちゃうんですよね。目指しているものができていない現状と向き合い続けなければならないし、そこから自分が無能だと思わされることだってある。喜びを感じられるのは、無事に納品できてクライアントが喜び、世の中で機能しはじめたときだけです。その最後の1%の喜びのために仕事をしています。
―イムさんでもそんなふうに考えることがあるんですね。
イム:自分が納得できる仕事をしていないと堂々としていられないんですよ。人に会いたくなくなるというか。だからこそ、より良い状態を目指すのですが、この年になってくると泥臭く自分を追い込みまくることはそんなにできない。そうは言っても、ものづくりは続けていきたい。そこで近くにいるスタッフに頼りはじめました。彼ら主導で仕事が進んでいくように取り組んだんです。いまではスタッフのほうが優秀だったりして、ちょっとは気楽にいれるようになりました。
―何かきっかけがあったんですか?
イム:私はずっと小さな会社であることにこだわってきました。欠員が出たら招き入れる。そうやってリスクを最小限にすれば、何か問題が発生して最悪の事態に陥っても、私財を投入すれば会社を維持することができるので。だから、創業から17年目が経ちますが、社員番号は40にも届きません。少人数にこだわり自分含めコアなところを弊社スタッフが担当できる体制に拘ってました。
―とても少ないですね。
イム:ただ、そうやって少人数のままだと自分たちに足りないスキルは社外パートナーに頼らなければいけないので、社内に知識や経験がなかなか蓄積されないんですね。それに社外パートナーもライフステージによる変化がありますから、同じ関係のままでいられる保証もありません。自分たちが考える最高の状態でものづくりをしていくためには、不安定なリソース状況から脱却するためにスタッフを増員しリーダー格スタッフを育てるほうが賢明だと考えるようになったわけです。それでこの数年は、人事制度や社内環境を整え、社員数を増やすことに注力してきました。この流れで在籍5年目、6年目になるリーダー格スタッフの制作物が世の中で評価されはじめていて。
―スタッフが育ってきていると。
イム:そうですね。私は舞台を用意して、はっぱをかけているだけの状態です(笑)。できたものを見て嬉しさでニヤニヤしています。
―つい口を出したくなりませんか?
イム:なりますよ。気になることがあったらすべて言いたくなってしまうんです。でも、それをやってしまうと成長の機会を奪うことになる。だから、できるだけ判断をスタッフに任せるようにしています。
―信頼できる存在がいる、と。
イム:そうです。現在は、私を除いた二つの大きなチームをつくれていて、複数のプロジェクトを進行しています。結局のところ、ものづくりにおいて重要なのは、強いビジョンを持ち、そこに引っ張っていく存在が真ん中にいるかどうかだと思うんですね。それができるリーダーたちが育ち、mountのなかでも中心となるべきなので、その立ち位置になれるように彼らにはとにかく高い水準を要求しています。これはリーダー格のスタッフたちだけにかぎらないことですが、これを続けると別の不安も生まれます。
―それは?
イム:スタッフが潰れてしまうかもしれないという不安です。圧倒的なクオリティを目指すのであれば、どこかで自分を追い込まなければいけません。私自身、そうして今まで仕事に取り組んできました。ただ、それは自分の話であって、他人ができるとはかぎらないですよね。
―自分で手を動かしてクオリティの高いものをつくるよりも難しいような気がします。
イム:そうだと思います。私と同じことができるのであれば、真似すればいいだけの話ですが、それは無理です。自分とは別の人間なわけですから。だから、スタッフには「あなたらしいリーダーシップを身につけてほしい」と伝えています。私は強い言葉を使うことが多いけれど、柔らかい言葉を使って引っ張っていくのも間違いではない。そうやって、それぞれが考える理想像を追いかけながら、次のステップに進んでいってほしいなと。そして、若い子たちを育てることも大切です。スキルを高めるための具体的な話だけでなく、「なぜこの仕事をやるのか」「なぜこの作業が必要なのか」といったことを強く意識してもらう必要があるので。考える機会をつくることも人を育てていくうえでは大切です。
―「なぜ」を突き詰めていくことで、会社としてつくるべきものの方向性が掴めてくるし、会社が大切にしているものが理解できるようになりますよね。
イム:無目的で仕事を強いられることほどしんどいことはないと思うんです。私自身、仕事が大変なときは「なぜこんなことをしないといけないんだ」と気持ちで落ち込むのですが、そんなときに自分を奮い立たせてくれるのは「なぜ」の部分なんですね。「よりよいものをつくりたい」とか「世の中に貢献したい」とか。そういう自問自答が必要だと思うんですよ。これを続けていくことで若い子たちが次のリーダーになれる。
自分がいなくなってもmountの文化が続いていくように
―イムさんの今後の取り組みとしては、やはり組織づくりが中心になっていくのでしょうか。
イム:そうですね。自分で言うのもなんですが、これだけものづくりに純粋に向き合えるデザイン会社は少数だと思うんです。自分自身にmountのような会社をもう一度つくれって言われてもできる自信がありません。そう考えるとmountがなくなってしまうのは、もったいない。
―道筋は見えているのでしょうか。
イム:頭のなかでぐるぐる考えているところです。今までは「俺が、俺が」でやってきたけれど、それをスタッフに引き継ぎ、mountの文化を残していく。そのために人事制度をもっと整える必要があるかもしれないし、お金の配分について考えなければいけないのかもしれない。売上目標も右肩上がりになるような設計にはしていないので、最悪を想定してリスクマネジメントする。売上を基準に誰かを評価しようとも思わないし、仕事においてどうなったら幸せなのかに対して広範囲に繊細に考えようと勤めています。とはいえ、今の状況を保つことが至難の業だとも思っています。
―ある程度やりきった感覚もあるのでしょうか。
イム:それはありますね。数年前にポートフォリオを眺めていたとき、ここまでやったら誰も文句は言われなさそうだなと。それくらい手を抜かずにやってきた自負があるんです。あとは今のものづくりの文化や環境が長く続いてくれたら、何も言うことはありません。幸運なことに自分の名前を社名につけていないので、年月が経って自分のことを誰も知らない状態になったタイミングでふらっとmountを訪れて、「いい会社だな」なんて言ってみたいですね。
______________
イム・ジョンホさんのパフォーマンスアップのためのルーティーン
「自分を一度落とす」
私はもともと怠け者で、仕事をしているとき以外の時間はどうしようもない。寝る時間も適当だし、お酒も大好き。とにかくだらしない人間なんです。だから、ルーティンと呼べるようなものは何もありません。ただ、そのダメな自分がいることで、仕事くらいはしっかりやろうという気持ちになるんですよね。そこでバランスを保っているというか。自分を底辺まで落とすことで、這い上がることができるんです。おすすめはしません(笑)。
イム・ジョンホさんのおすすめのワークツール
「腕時計」
40歳を超えていい歳のおじさんになったから、いい腕時計でも身につけようと思って1年前に購入したのが「A.ランゲ&ゾーネ」。デザインのバランスが完璧すぎて、文句のつけようがありません。見ていて惚れる、機能美に優れた腕時計です。身につけているだけでテンションが上がります。
LOGIC | CULTURE
教養としてのカルチャーを楽しみながら学ぶ。

「アートのロジック」第11回
『岡本太郎』
「今日の芸術は、うまくあってはいけない。きれいであってはいけない。ここちよくあってはいけない」。これは、20世紀の日本を代表する芸術家・岡本太郎(1911〜96)が1954年に刊行したベストセラー『今日の芸術』のなかで記した有名な一説です。
芸術とは技術的に巧みで、見た目に綺麗で、人の癒しとなるものだ——。そんな、現在至るまで日本社会に広がっている穏当な芸術観を、太郎は一蹴。自身の作品や言葉、生き方を通じてその価値を転倒し、芸術の本質を問い続けました。その思想は前衛を志す若い芸術家を鼓舞しただけでなく、「芸術は爆発だ」という言葉や、大阪の万博記念公園に立つ巨大な《太陽の塔》(1970)などを通して、広く戦後の日本に影響を与えています。
では、太郎のこうした芸術観はどのように形成されたのでしょうか? その点に関してまず非常に大きいのは、彼が10代の終わりから約10年間を過ごしたパリでの体験です。
太郎は1911年、現在の神奈川県川崎市に生まれます。父の岡本一平は人気漫画家、母のかの子は歌人という芸術家一家で、父の放蕩癖や、母の愛人との共同生活など、型破りな暮らしでも知られます。こうした環境で早くから自由さと芸術への意志を育んだ太郎は、18歳となった1929年、同年春に入学した東京美術学校(現・東京藝術大学)をわずか半年で退学すると、父のロンドン取材に同行して渡欧。パリで一人、芸術活動を始めます。
1932年、画廊でピカソの《水差しと果物鉢》を見た太郎は、帰り道に涙が止まらないほどの感動を覚えたといい、以後、抽象画を志向。翌年、ヴァシリー・カンディンスキーやピート・モンドリアンといった抽象画の巨匠、盟友クルト・セリグマンらが名を連ねる「アプストラクシオン・クレアシオン(抽象・創造協会)」に最年少で参加します。しかし、マックス・エルンストらシュルレアリスム運動の芸術家とも交流していた彼は、次第に純粋抽象に限界を感じ、リボンを付けた人物を描いた《傷ましき腕》(1936/1949)の発表を機に協会を脱退。同作をアンドレ・ブルトンに賞賛されると、彼が率いていたシュルレアリスムの活動に合流しました。
こうして、抽象画とシュルレアリスムという当時最先端の2つの動向に深く関わりながら、太郎は自身の思想をかたちにしていきます。それが結実したのが、戦後に標榜した「対極主義」です。
合理的な抽象画と、非合理的なダダやシュルレアリスム。太郎は、矛盾する方向性をもつ両者を安易に混合したり、融和したりするのではなく、むしろその矛盾をとことん深めることで生まれる緊張のうちに「前進」があると考えました。ともに対照的なモチーフや色を画面に置いた戦後の作品《重工業》(1949)や《森の掟》(1950)は、彼のこうした考えを代表する作品です。そして、相容れない要素が対峙することで生まれるエネルギーへの志向は、例の「芸術は爆発だ」をはじめ、彼の活動の端々に現れることになります。
太郎がパリで交流したのは芸術家だけではありません。1936年には上述のエルンストとともに革命的知識人の政治集会に参加し、そこでエロティシズムと生死の研究や、西欧批判の言説で知られる思想家ジョルジュ・バタイユの演説に感動。のちに彼の秘密結社「アセファル」に参加し、深夜の森での「儀式」も体験します。さらに並行して、パリ大学で民族学を学び、『贈与論』で知られる文化人類学者のマルセル・モースに師事。太郎の、芸術は商品ではなく、無償、無条件のものであり、全人間的なものだという思想や、社会において呪術的なものが果たす役割への関心は、ここで大きく育まれたとされます。
パリで異邦人として過ごし、民族学を学んだ太郎にとって、日本の伝統や日本に暮らす人たちのルーツは重要な関心事でした。そんな彼に衝撃を与えたのが、 1951年に東京国立博物館で見た縄文時代の火焔型土器です。激しく隆起し、入り組んだその文様に「思わず叫びたくなる凄み」を感じた彼は、それを「わび・さび」などに代表される日本の情緒的で形式的な価値観に対置。縄文土器に見られる原始の時代の、可視の世界と不可視の世界を超えた「四次元との対話」に、現代に打ち立てるべき「新たな伝統」を主張しました。
縄文土器の美の「発見」のあと、太郎は東北や沖縄など各地を調査旅行で訪れ、そこに残る風土、祭りや原風景を文章や写真に残しました。そして、縄文土器から受けた衝撃や、こうした民族学的なフィールドワークを経て生まれたのが、1970年、大阪万博(日本万国博覧会)の中心たるテーマ館の一部として制作され、現在も残る《太陽の塔》です。
参加国77カ国、総入場者数約6400万人を数えた大阪万博は、戦後の日本の成長を象徴する国家イベントでした。《太陽の塔》はこの祭典の象徴として制作されますが、その造形が万博のテーマ「人類の進歩と調和」への疑問を源泉とすることはよく知られています。太郎は当時の日本の好調を示すようなこのテーマに堕落と妥協を感じ取り、そこに近代的な進歩とは真逆の原始的な造形を、しかも、未来的な大屋根を突き破るほどの巨大さで打ち立てることで、日本が豊かになるなかで見失われていた人間性の回復を問うたのです。
《太陽の塔》は、当時の美術界からは等閑視されますが、大衆には受け入れられ、太郎はこの万博を機に、公共的な仕事やマスメディアへの露出を増やしていきます。また、万博後にはパブリックアートの依頼も増え、もともと芸術は「太陽」のように誰もが触れられるものであるべきという考え方を持っていた太郎は、この要望に積極的に応えました。極めて前衛的でありながら、誰よりも人前に自身を晒し、大衆的であること。こうした両義的な振る舞いにも、異なる要素の同存に賭ける「対極主義」が感じられます。
こうして、人生の後半を大衆と対峙して過ごした太郎ですが、その思想や芸術がここまで多くの人を惹きつけたまたひとつの要因として、長年彼の秘書を務め、後に養女となりその活動に伴走した、岡本敏子の存在は欠かすことができません。例えば、その作品と同じほど人気が高い太郎の魅力的な著作の多くは、彼が語った言葉を文学少女だった敏子が口述筆記したものといわれます。また、1960年代にメキシコで計画されたホテルのために制作されるも、計画の頓挫後に行方不明となった巨大な壁画《明日の神話》(1968-69)を捜索の末に見つけ出し、2008年に渋谷駅に設置される道筋を付けたのも、敏子でした。
そんな《明日の神話》は、1954年にアメリカの水爆実験によって被曝した第五福竜丸事件を主題とする作品で、画面には原爆が炸裂する瞬間が描かれています。しかし、敏子が生前残したメッセージの通り、そこには悲惨さだけでなく、悲劇を乗り越えて進む人間の誇らしさや力強さも刻まれています。破壊と創造、醜と美、死と生……矛盾から生まれるエネルギーにこそ、真の芸術は宿る。そんな太郎の思想は、いまも人々を鼓舞しています。
【参考文献】
「特集=岡本太郎」『美術手帖』2011年3月号、美術出版社
佐々木秀憲『もっと知りたい岡本太郎 生涯と作品 (アート・ビギナーズ・コレクション) 』東京美術、2013
「岡本太郎とは」岡本太郎記念館ホームページ(https://taro-okamoto.or.jp/taro-okamoto/)
杉原 環樹
1984年東京生まれ。武蔵野美術大学大学院美術専攻造形理論・美術史コース修了。出版社勤務を経て、現在は美術系雑誌や書籍を中心に、記事構成・インタビュー・執筆を行う。主な媒体に美術手帖、CINRA.NET、アーツカウンシル東京関連。編集協力として関わった書籍に、卯城竜太(Chim↑Pom)+松田修著『公の時代』(朝日出版社)など。
(この記事は2024/8/6にNewsletterで配信したものです)