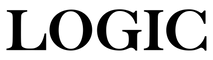LOGIC MAGAZINE Vol.37

LOGIC | PEOPLE
第一線で活躍するプロフェッショナルの体験や知見から
パフォーマンスアップにつながるヒントを学ぶ。

037
POST COFFEE株式会社
下村 領氏
LOGIC MAGAZINE第37回インタビューにご登場いただくのは、スペシャルティコーヒー専門のオンラインストアやサブスクリプションサービスなどを手がけるPOST COFFEE株式会社の下村 領氏です。コロナ禍で大きくサービスを拡大し、実店舗の運営まで乗り出した同社の現在に至るまでの軌跡と下村氏の目指す理想形について尋ねます。(聞き手:LOGIC MAGAZINE編集部 佐々木、村上)
コーヒーと消費者の距離を
もっと縮めていきたい
―2020年のサービスリリースから約4年が経ちました。現在は日本最大級のスペシャルティコーヒー専門のオンラインストア、そしてサブスクリプションサービス、さらには下北沢で実店舗の運営まで手がけています。下村さんはもともとデザイン会社を経営されていて、異業種での起業だったわけですが、この4年を振り返るとどのような年月でしたか?
下村:面白さもあり、大変さもあり、という感じでしょうか。デザインの仕事は受注で成り立っているので、長くても1年とか2年でプロジェクトが終了します。でも、事業となると自分たちが続けていくかぎりは関わっていかなければならないんですよね。しかも、デザインの仕事は原価がほぼゼロでしたが、物を売る仕事はいろんなことを管理しながら取り組まないといけません。だから、バイオリズムの振れ幅が激しいと言いますか。天と地を行ったり来たりしているような感覚があります。
―需要と供給の波を読むのは難しいですよね。予測通りにならないことも多いでしょうし、外的要因が絡んで自分たちの力だけではどうすることもできない事態もあるわけですよね?
下村:まさに。今だと世界的にコーヒー豆の原価が上昇しているのですが、そうした社会情勢を考慮して値上げに踏み切るべきか、それとも我慢するべきかに頭を悩ませています。
―お客さまとの信頼関係のことを考えたら、10円上げるだけでも大きな決断になりますよね。
下村:我々としても高品質のものをできるだけ低価格で提供したい気持ちはあるんですね。お客さまもそれを望んでいるはず。一方で、売上が立たなければ事業を継続できません。これまでは値段を据え置きで内容量を増やすなどの工夫をしてきましたが、今後についてはまだ定まっていないことも多いですね。ただ、私たちのサービスを愛用してくださるお客さまが大勢いるので、辛いことがあっても頑張ることができている気がします。
―お客さまがいることがモチベーションに?
下村:はい。僕はもともとコーヒーやその周辺にある音楽やファッションが好きで、カフェに足を運ぶと気分が上がるタイプなんです。だから、高揚感を得られるものを自分たちの手で生み出し、お客さまに提供できることはものすごくモチベーションになっています。
―POST COFFEEのサブスクリプションは、コーヒー豆の種類や1袋あたりの量を自由にカスタマイズできるのが魅力ですが、コーヒー豆はどのように用意しているのですか?
下村:目黒に自社工場があり、そこで焙煎やパッキングなどを自社で賄っています。3PL(サードパーティー・ロジスティクス)も試してみたのですが、弊社のサービスの場合、何万通りも組み合わせがあり、しかもお客さまそれぞれに量や種類、焙煎の仕方も異なります。これを3PLで実現しようとするとコストが跳ね上がってしまうんですね。原価を1円でも下げることを考えると、内製するのが今の段階でのベストな選択だと考えています。
―POST COFFEEがリリースされた2020年頃はD2Cブームでしたよね。今は少し落ち着いたと思うのですが、事業の進め方に変化はありますか?
下村:それこそ2020年から2022年にかけては、オンライン広告を配信すると比較的良いCPA(顧客獲得単価)でお客さまを獲得できていました。2023年頃からその数字が悪化してきたこともあり、お客さまの口コミやメディアでの紹介、そして小売店での販売がブランド認知の入り口になるようにしています。広告費もほぼかけないようにしていますね。
―広告費をかけない、というのは面白いですね。
下村:広告費って依存性の高い特効薬みたいなものだと思うんです。使っている間はある程度の数字が見込めるからやめるのが怖くなる、みたいな。でも、大きな結果が出ない状態で使い続けるのは、会社として健全ではないですよね。それに今後はオフライン施策がより重要になると思うんです。食品の国内EC化率は4%未満だと言われていて、裏を返せば96%はオフラインということになります。だからこそ、卸売は強化していきたいなと。
サブスクの大量受注により業務過多に。店舗運営を一時諦めることに
―とすると、下北沢に実店舗を構える構想はもともとあったのでしょうか?
下村:話は少し長くなるのですが、実はデザイン会社を経営しているときに渋谷の富ヶ谷で実店舗を経営していたことがあるんですよ。今はもうないんですけれど。
―なぜお店を閉めることになったのでしょうか?
下村:2020年の2月にPost Coffeeをスタートして、しばらく経って緊急事態宣言が発令されたタイミングでプレゼント企画を実施したんですよ。そうしたらサブスクリプションの登録が一気に増えてしまって、朝から晩まで毎日のようにコーヒー豆を梱包して郵便局に持っていく作業を繰り返すことになりました。それでようやく落ち着いたと思ったら、今度はテレビで取り上げられて、再び数千件を超える注文が入ってしまって(笑)。
―嬉しい悲鳴ですが、そんなことも言っていられない状況になってしまったわけですね。
下村:当時は本当に大変でしたね。うちのサービスは、豆の種類から挽き方に至るまでパーソナライズできるので、お客さまごとに対応する必要があります。しかも、当時はシステムが整っていなかったこともあり、対応がどんどん遅れていきました。当時のお客さまには本当にご迷惑をおかけしたと思います。そんな状態が半年ほど続いたこともあり、実店舗は一旦閉めよう、と。それから体制を立て直して安定もしてきたので、あらためて実店舗をオープンするに至りました。ただ、現在はキャパシティの限界も見えはじめていて。これからさらに事業を拡大するとなると、新たに設備投資が必要になります。それには資金が必要なので、どのタイミングで調達するべきなのかを検討している状況です。
―ちなみに、コーヒーは“儲からないビジネスのひとつ”だと言われていますよね。事業拡大を目指さずに小規模のまま経営していく選択肢もあったと思うのですが、何が下村さんを突き動かす原動力になったのでしょうか。
下村:立ち上げる前までは小規模で経営していく予定だったんです。でも、2019年にアプリのベータ版をリリースしてローンチパーティーを開いたところ、想定以上に人が集まったんですね。その光景を目の当たりにして、大きく展開していくことを決めました。これはいけるのではないかと。あと、過去にスタートアップ企業のCTOを務めた時期があり、資金調達から売却まで経験したことがあるんですね。そのダイナミズムをもう一度味わってみたい気持ちもありました。

POST COFFEEが目指すのは“なんとなくいい”世界観の構築
―下村さんのなかでPOST COFFEEの理想像はどのようなものですか?
下村:コーヒー屋さんってお客様にストーリーを伝えて売っていくスタイルが多いと思うんですね。ただ、それだけだとなかなか広まりにくいなという実感があって。それは以前、渋谷で店舗を経営していたときに感じたことなんですけれど。そうではなく、“なんとなくいいよね”という切り口から興味を持ってもらうスタイルをつくりたいと考えています。そのためには、うんちくを語らないで、なんとなくイケてる感じが必要なんじゃないかなと。
―その“なんとなくいいよね”は言語化されているものなんですか?
下村:会社のバリューのひとつに「HYPE STANDARD」というものがあって。「HYPE」はファッション界隈で最近使われるようになった言葉なんですが、そのHYPEな感覚を写真やグッズにインストールさせています。その空気感を肌で感じてもらえればいいなと。
―その世界観が広がっていくと、理想に近づいていくことになるわけですね。これから実現したいことはありますか?
下村:POST COFFEEは「美味しいコーヒーと、消費者を、最短距離で繋ぐ。」をミッションに掲げているのですが、その距離はまだまだ遠いので、少しでも縮めていければと考えています。今後コーヒーフェスみたいなものを全国各地で開催していきたいと考えているのですが、そういう文脈で美味しいコーヒーに近づいてもらうとか、全自動コーヒーメーカーを使って簡単に美味しいコーヒーを提供できるようにするとか、いろいろ考えています。
―このままPOST COFFEEのカルチャーが10万人、20万人の規模まで拡大していくと、おもしろいことが起きそうですね。
下村:そうですね。お客様のなかには海外から転送サービスを使って注文してくださる方もいて。そういう反応を見ると、中国や韓国といったアジア圏でもサービスを拡大できる可能性はあるはず。日本と比べてマーケットの成長スピードも早いですし、うまくローカライズして持っていけたらと密かに構想を練っています。

______________
下村 領さんのパフォーマンスアップのためのルーティーン
「バイクに乗る」
もともとアウトドアが好きで、なかでも最近はバイクに乗ることに夢中です。一歩間違えれば命の危険に遭う可能性もあるので気が抜けないのですが、だからこそ、その時間だけは仕事のことを忘れることができるので気分転換に最適なんです。週末になるとハイエースにバイクを乗せて、関東圏内にあるサーキット場やオフロード走行ができる場所まで出向いています。
下村 領さんのおすすめのワークツール

「KEES VAN DER WESTENのエスプレッソマシン」
人生を変えるきっかけになったエスプレッソマシンです。あるときネットサーフィンをしていたら一目惚れしてしまって。100万円以上したのですが、思わず購入してしまったんです。職人による受注生産だったので、注文してから半年経ってようやく完成。ついに手に入ると喜んだのも束の間、個人輸入が珍しかったことから税関をうまく突破できず、半年間ほど税関の倉庫で保管されることになりました。ようやく届いたのは、発注してから1年後のことでした。でも、このエスプレッソマシンは当時とても珍しかったので、いろんなバリスタが遊びに来てくれて横のつながりができるきっかけになりました。ただ、その当時はコーヒー豆のことをよく知らなくて、この時期に知り合ったLIGHT UP COFFEEの川野優馬くんから笑われるほどでした(笑)。彼から美味しい焙煎豆を手に入れたことが、スペシャルティコーヒーの魅力をもっと多くの人に伝えたいと思うきっかけになっています。
LOGIC | CULTURE
教養としてのカルチャーを楽しみながら学ぶ。

「ビジネス映画学」第10回
『復讐 運命の訪問者』
2024年は、”黒沢清監督イヤー”と言えるかもしれません。実際、『蛇の道』を皮切りに『Chime』『Cloud クラウド』と3本もの新作が公開されたのですから。しかも、ただ多作というだけでなく、『Chime』『Cloud クラウド』はそれぞれベルリン国際映画祭、ヴェネチア国際映画祭と世界三大映画祭の2つに招待されており、クオリティも折り紙付き。なぜ、そんな快挙が成し遂げられるのでしょうか。今回は、1997年制作のVシネマ『復讐 運命の訪問者』を通して、黒沢監督の類稀なる仕事術に迫ってみたいと思います。
本題に入る前に前述したVシネマについて解説しておきましょう。それは90年代の日本で活況を呈した、レンタルビデオ屋で流通させることを前提に作られた映画のこと。とりわけその中心を担っていたのはヤクザ映画です。制作費は少ないものの、ヤクザさえ出てくれば後は何をしてもいいVシネマは、作家性の強い若手監督の登竜門をなし、ここから現在の日本映画界を代表する監督に上り詰めた人も少なくありません。『復讐 運命の訪問者』もそんなVシネマの一本です。
主人公の安城伍郎を演じるのは、当時のVシネマのスター哀川翔。安城は幼い頃、会社の問題に巻き込まれた父に加え、母と姉を何者かに惨殺された過去を持ちます。押入れに隠れることで一命を取り留めた安城が、大人になり今は刑事として働く中、とある事件を通して出会ったのが、宮地兄弟です。
宮地兄弟はクリーニング屋を営む傍ら、刑務所から出所してきた前科者たちの保護司としても働いています。しかし、それは表向きであって、実はヤクザ向けの殺し屋人材派遣業者という裏の顔がありました。そのことを突き止めた安城は、刑事を辞めて復讐することを誓うのですが、見逃してはならないのは、宮地兄弟が仕事において”何足ものわらじ”を履いているということ。それは黒沢監督の仕事術を象徴するキーワードでもあるからです。
例えば、クライマックスの一歩手前に置かれた銃撃戦のシーンを見てみましょう。安城は人質にとったヤクザの1人と、宮地兄弟らが潜伏する廃墟の前に車を停めます。安城がヤクザに銃を突きつけながら車を降りて数歩進むと、画面外から登場したのはかつての同僚刑事です。元同僚は安城を止めるために銃を向けてゆっくり迫ってくるのですが、その瞬間、廃墟の中で響くのは一発の銃声。一同が身をかがめた隙をつき廃墟の中に走り去るヤクザを、安城は追おうとしますが、元同僚に制止されて身動きが取れません。なんとか引き離した安城は、元同僚に向けて銃弾を放ちます。防弾チョッキを着ているから、重症にはならないだろう、と。ところが、元同僚は安城が自分には銃を撃たないと信じていたため、なんと防弾チョッキを着てないと言うではないですか。しかし、安城は復讐を果たさねばなりません。息絶えた元同僚を置き去りにし、暗くなっていて中の見えない廃墟へと入っていく安城。その動きに合わせて、これまで廃墟の手前に固定されていたカメラは、その位置のまま横移動を開始します。中で何発かの銃声が響くと、入り口から飛び出してきた敵の1人を、安城が撃ち殺します。
なぜ、ここまで細かくシーンを描写したかといえば、このすべてがたったひとつのショットの長回しで撮られているからに他なりません。ごく一般的なハリウッド映画であれば、途中で安城と元同僚のアップを挿入するなど、カットを割るでしょう。しかし、黒沢監督はそれを息の長いひとつのショットの中に収めてしまう。長回しは本作の他のシーンを含め、黒沢監督がよく使う手法であり、監督自身が折に触れて解説している言葉を総合すれば、それには次に何が起こるのかわからない不穏な緊張感を際立たせる効果があります。
しかし、この長回しの多用は、純粋に映画的な効果を狙っただけではないようです。監督はこう語っています。「商業映画は1日10〜15カットしか撮影できない、というわかりやすい原則があるのです。太陽が出て沈むまで、動かしようのない時間の制約があります。それで予算がなくスケジュールがコンパクトな映画を撮るためには、1シーンに3カットしかかけられないのです。ピストルで撃って打たれて逃げるまでのカットをワンカットで撮れる、現場での切実な悩みをワンカットでやる」。
つまり、黒沢監督にとって長回しは、芸術的な効果と同時に、コスパ&タイパをも追求できる、まさに”二足のわらじ”が履ける手法なのです。
ゆえに、黒沢監督は撮るのが早い。「よほど特殊な撮影でない限り、朝の7時か8時頃に撮影を始めて、夕方の5時までには必ず終わっています」と監督自身も語っているように、過酷な労働環境が問題視されがちな日本の映画業界において、黒沢監督の現場は異例なほど”ホワイト”として知られます。だからこそ、年に3本もの新作を公開できるのでしょう。
徹夜も覚悟で時間を掛けなければ、優れた商品は生み出せない。映画業界に限らず、日本社会にはそんな商慣習が根強く残っています。確かに、そういう側面がないとは言いません。しかし、早撮りで尚且つ世界的にも評価されている、黒沢監督の”2足のわらじ”を履く仕事術は、それを打開する可能性を指し示しているのではないでしょうか。
鍵和田 啓介
1988年生まれ、ライター。映画批評家であり、「爆音映画祭」のディレクターである樋口泰人氏に誘われ、大学時代よりライター活動を開始。現在は、『POPEYE』『BRUTUS』などの雑誌を中心に、さまざまな記事を執筆している。
(この記事は2024/09/30にNewsletterで配信したものです)